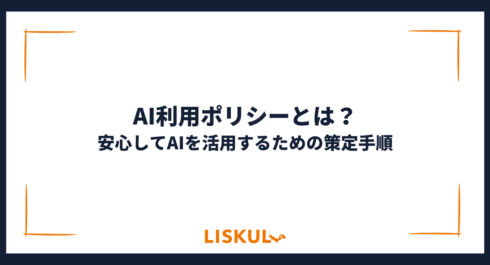
AI利用ポリシーとは、生成AIや機械学習モデルを業務で活用する際に守るべき原則と手順をまとめた社内規程です。
このポリシーを整備することで、情報漏えい・法令違反・ブランド毀損といったリスクを抑えながら、AIによる生産性向上や新しい価値創出を実現できます。
一方、ルールがない状態でAIを使い始めると、機密データの流出や著作権問題が発生し、最悪の場合はAI活用そのものが社内で禁止される恐れもあります。
そこで本記事では、AI利用ポリシーの基礎、策定手順、国内外の事例、よくある誤解への対処法までをまとめて解説します。
AIを安全かつ効果的に導入したい方は、ぜひご一読ください。
【早見表】生成AIサービス主要20選(2025年版)【社内共有OK】
目次
AI利用ポリシーとは
AI利用ポリシーは、生成AIや機械学習モデルを業務に取り入れる際に守るべき原則と運用手順を定めた社内規程です。
情報漏えい・法令違反・ブランド毀損などのリスクを抑えつつ、生産性向上や新規価値創出を最大化することを目的としています。
参考:生成AIのAPIの基礎から料金比較まで一挙紹介!|LISKUL
AIガバナンスとは?概要や重要性をわかりやすく解説|LISKUL
対象範囲
外部のチャットボットや画像生成ツールから自社開発モデルまで、AI技術を利用するすべての業務プロセスが対象です。
適用範囲は経営層・従業員・委託先まで含まれます。
整備の意義
AI利用ポリシーを整備する意義は主に以下の2つです。
- 個人情報保護法・著作権法・EU AI Actなど国内外の規制を安全網として組み込み、現場が安心してAIを活用できる明確なルールを示すことで、意思決定の速度と業務効率を同時に向上させます。
- ISO/IEC42001(AIマネジメントシステム規格)や取引先監査への備えとなり、資金調達や大口案件獲得の場面で信頼性を証明できます。
従来との違い
従来の情報セキュリティポリシーやAIガイドラインが「技術管理」や「望ましい行動」にとどまるのに対し、AI利用ポリシーは「誰が」「どのAIを」「どのデータで」「どの手順で使うか」を具体的に定義します。
ガバナンスと実務を橋渡しする仕組みとして、運用プロセスに落とし込みます。
ビジネス価値
ポリシーを整備した組織は、社内外の不安を払拭しながらAI導入を加速できます。その結果、イノベーション創出のスピードで競合優位を獲得しやすくなります。
AI利用ポリシーが注目される背景にある4つの要因
生成AIの普及が想定以上のスピードで進んだ結果、法規制・リスク・ステークホルダーからの要請が同時に高まり、企業は「まず作るべき社内規程」としてAI利用ポリシーに注目しています。
1.国内外で進む規制強化と法整備
EU AI Actをはじめとする海外規制の施行予定が相次ぎ、日本でも経済産業省や個人情報保護委員会がガイドラインを改訂しています。
グローバルに事業を展開する企業は、複数の法域を横断して適合させる必要があり、統一的な社内ポリシーがないと対応コストが跳ね上がります。
参考:EU AI Act
2.情報漏えい・コンプライアンス事故の増加
ソースコードや機密文書を生成AIへ誤入力し、外部に流出した事例が大手企業でも報じられました。
事故を経験した企業が一時的にAIツールを全面禁止するケースもあり、「使いながら守る」ための具体的ルール整備が急務となっています。
参考:コンプライアンス対策で実施すべき12の項目を優先順位順に解説
|LISKUL
3.取引先・投資家が求めるガバナンスと透明性
サプライチェーン全体でAIリスクを共同管理する動きが広がり、コンプライアンスチェックの項目として「AI利用ポリシーの有無」を確認される場面が増えています。
ポリシーを提示できないと受注や資金調達の段階で不利になるため、経営レベルの課題になっています。
4.生成AI活用シーンの爆発的拡大
チャットボットによる顧客対応、営業資料の自動生成、プログラミング支援など利用範囲が一気に広がり、従業員の自己判断に任せるとリスクが拡散します。
安全に活用機会を増やすため、社内で統一された判断基準としてポリシーが求められています。
ポリシー未整備が招く4つのリスク
AI利用ポリシーを整備しないまま生成AIを導入すると、ビジネス価値を高めるどころか情報漏えい・法的責任・ブランド失墜といった深刻な損失を招きます。
最悪の場合、AI活用自体が全社的に凍結され、競合との差が一気に開くおそれがあります。
1.情報漏えいと機密データの拡散
従業員が機密資料や顧客データをそのまま外部AIサービスに入力すると、学習データとして第三者に再利用される可能性があります。
流出した情報は回収不可能で、新製品の設計図や未公開の財務情報が競合に渡るリスクすら考えられます。
2.法的・コンプライアンス違反
生成AIが作成したコンテンツに第三者の著作物が含まれていた場合、著作権侵害を問われる恐れがあります。
また、不適切な個人情報の取り扱いは個人情報保護法やGDPRの制裁対象となり、巨額のペナルティや訴訟費用が発生しかねません。
参考:GDPRとは?今すぐ対応すべき企業と最低限実施すべき5つの対策
|LISKUL
3.ブランド毀損とステークホルダーの信頼喪失
AI起因の事故はメディアの注目度が高く、一次対応が遅れると「責任あるAI運用ができていない企業」としてレピュテーションが大きく下がります。
投資家・取引先・求職者からの評価低下は、売上や採用コストに直結します。
4.生産性低下とAI全面禁止リスク
安全策がないまま導入し問題が発生すると、経営判断でAI利用が一律禁止されるケースが珍しくありません。
これにより最も影響を受けるのは現場で、せっかく芽生えたAI活用カルチャーが萎縮し、イノベーション機会を逃す結果になります。
AI利用ポリシー策定のゴールと5つの必須要素
AI利用ポリシーの目的は、AIの利点を最大限に引き出しつつ経営リスクを可視化・制御することです。
本章では、その目的を達成するために不可欠な要素を整理し、策定時に漏れのないチェックリストとして活用できるようにまとめます。
ビジネスゴール:リスク最小化と価値最大化
ポリシーは「守るための規則」だけでなく、売上向上やコスト削減などAI導入で狙う成果を明文化し、それを阻むリスクを先回りで管理する枠組みとして設計する必要があります。
必須要素1.適用範囲と対象AIの明示
チャットボット、画像生成、コード補完など具体的なツール名やバージョンを列挙し、利用できる部署・ロール・端末を定めることで従業員が判断に迷いません。
必須要素2.データ取り扱いルールとセキュリティ基準
入力可能な機密レベル、外部送信できるデータ種別、暗号化方式、保存期間などを規定し、ログ管理やアクセス権設定といった技術基準も合わせて示します。
必須要素3.禁止事項と例外申請プロセス
著作権保護コンテンツの無断入力、個人情報の未加工アップロード、モデル出力の無断転載など具体例を挙げ、やむを得ない場合の例外申請フローを用意して統制と柔軟性を両立させます。
必須要素4.教育・啓発と責任体制
入社時研修や定期テストで理解度を測り、違反時の一次対応者と最終責任者を組織図上に明示して「誰が判断するか」を明確にします。
必須要素5.監査・改善サイクル
四半期や半期ごとの内部監査で遵守状況を確認し、規制や技術の変化に合わせて改訂するサイクルを設定します。
履歴を残すことで外部監査や取引先からの問い合わせにも迅速に対応できます。
AI利用ポリシーを策定する方法6ステップ
AI利用ポリシーは「6ステップ」で体系的に策定できます。
まず現状と目的を定義し、リスクを洗い出した上でドラフトを作成、関係者の承認と教育を経て継続的に改善する流れを押さえれば、大企業でもスタートアップでも無理なく導入可能です。
ステップ1:現状把握と目的設定
最初に、どの部門がどのAIツールを利用しているかを棚卸しすると同時に、「コスト削減」「業務効率化」「新規事業創出」など期待する事業インパクトを定めます。
目的を数値目標(例:年間工数を20%短縮)に落とし込むことで、後のKPI設計とポリシー評価がスムーズになります。
ステップ2:リスクアセスメント
対象AIと取扱データを整理したら、情報漏えい、著作権侵害、アルゴリズムバイアスなどのリスクを洗い出し、発生確率と影響度で優先順位を付けます。
リスクレジスターを作り、既存の情報セキュリティ体制と突き合わせることで、追加で必要な統制や技術的対策が明確になります。
ステップ3:ベンチマークとドラフト作成
ISO/IEC42001や先進企業の公開ガイドラインを参照し、自社の業種・規模に合わせて項目を取捨選択しながらドラフトを作成します。
この時点で「適用範囲」「禁止事項」「例外手続き」「監査方法」の4要素が抜けていないかをチェックリストで確認してください。
参考:ISO/IEC42001
ステップ4:ステークホルダーレビューと経営承認
法務・情報システム・人事・各事業部のキーパーソンがレビューを行い、実務上の抜け漏れや運用負荷を調整します。
最終的には経営層の承認を得ることで、組織全体への強制力とリソース確保が担保されます。
ステップ5:社内教育と周知
承認後は、イントラ掲載と対面/オンライン研修を組み合わせ、従業員が「何をしてよいか・いけないか」を即答できるレベルまで浸透させます。
理解度テストやeラーニングを設定し、合格を利用許可の前提条件にすると遵守率が高まります。
ステップ6:モニタリングと継続的改善
導入後は四半期ごとにログを分析し、違反件数やAI活用率などの指標で効果を測定します。
規制改正やツール更新に合わせてドラフトを改訂し、最新版を再教育するサイクルを回すことで、ビジネスとガバナンスの両立が持続的に実現できます。
AI利用ポリシーの事例
生成AIの導入フェーズや業種によってポリシーの重点は変わります。ここでは「グローバル大手×日本企業」の4社を取り上げ、特徴と学べるポイントを整理しました。
各項目末尾の出典番号をクリックすると、企業が公開している原文ページにアクセスできます。
マイクロソフト:Responsible AI Standard
同社は「公平性・信頼性と安全性・プライバシーとセキュリティ・包括性・透明性・説明責任」の6原則を中核に、プロダクト開発前後で40超のチェック項目を設けています。
リスクに応じて「低・中・高」の3段階で文書化レベルを変える仕組みが特徴で、モデルのブラックボックス化を避けるための“透明性ドキュメント”の公開が義務付けられています。
参考:Responsible AI Principles and Approach|Microsoft AI
IBM:Everyday Ethics for AI
IBMは「信頼できるAI」を掲げ、Explainability(説明可能性)とUser-Centric Design(利用者中心設計)を強調します。
開発者向けに日常業務で使える「質問テンプレート」を提供し、データ収集から運用まで各工程で倫理チェックを行う“Ethics by Design”を徹底。
AI倫理委員会が全社横断でレビューする体制も整備しています。
参考:Everyday Ethics for Artificial Intelligence
Responsible AI|IBM
NTTグループ:AI憲章・ガバナンスポリシー・生成AI利用ガイドライン
国内通信大手のNTTは2024年にAI憲章(理念)→AIガバナンスポリシー(仕組み)→生成AI利用ガイドライン(実務)の三層構造を発表。
リスクベースアプローチで「法令違反・契約違反・社会的批判」の3カテゴリを管理し、グループ各社に共通のチェックリストを配布して運用を標準化しています。
参考:AIガバナンス |NTTのAIについて |NTTグループの取組み
NTTグループのAIガバナンス規程類の制定、およびAIガバナンスの推進体制について~お客様が安心して利用できるAIの提供に向けたCo-CAIO、AIガバナンス室の新設~ | ニュースリリース |NTT
日立製作所:社会イノベーション向けAI倫理原則
インフラ事業を多く抱える日立は、社会への影響の大きさを踏まえた「計画・社会実装・維持管理」の3フェーズ別行動規準と、安全性・公平性・プライバシーなど7つの実践項目を策定。
研究開発段階から現場運用まで同じ原則を適用し、事業部横断でリスクアセスメントを行うプロセスを確立しています。
参考:社会イノベーション事業のための日立のAI倫理原則とその実践 : 日立評論
AI利用ポリシーに関するよくある誤解5つ
最後に、AI利用ポリシーに関するよくある誤解を5つ紹介します。
誤解1「無料の生成AIならリスクはゼロ」
利用料の有無と法的・技術的リスクは無関係です。学習データへの再利用や第三者提供に関する条項は有料プランと変わらない場合が多く、情報漏えいや著作権侵害のリスクは残ります。
料金ではなく利用規約とデータ処理方針を必ず確認しましょう。
誤解2「機密情報を入力しなければポリシーは不要」
たとえ一般公開情報だけを扱う場合でも、AIが生成したアウトプットが誤情報や差別表現を含む可能性があります。
監査ログや利用承認フローを設けなければ、説明責任を果たせずブランド毀損を招く恐れがあります。
誤解3「ポリシーは一度作れば改訂しなくてよい」
規制も技術も半年単位で更新されます。改訂を怠ると、現場の運用が最新の法令や社内システムに追いつかず形骸化します。
改訂時期と責任者をポリシー本文に盛り込み、定期レビューを前提とした仕組みを作ることが重要です。
誤解4「技術部門が決めれば十分」
AI利用はコンプライアンス・人事・営業など多部門に影響します。たとえば営業資料に生成AIを使う場合、法務による契約チェックやブランドガイドラインとの整合が欠かせません。
他職種を巻き込んだ委員会形式で策定することで、運用負荷とビジネス要件の両立が可能になります。
誤解5「外部ツールを全面禁止すれば対策完了」
禁止策は短期的な安全網に見えても、従業員の“隠れ利用”を誘発しシャドーITを拡大させるリスクがあります。
安全な利用方法を提示し、承認済みツールをホワイトリスト化するほうが実効性の高い統制になります。
まとめ
本記事では、AI利用ポリシーの基本概念から策定手順、国内外企業の具体例までを一挙に解説しました。
AI利用ポリシーとは、生成AIや機械学習モデルを業務で活用する際に必ず守るべき原則と運用手順を示す社内規程であり、情報漏えい・法令違反・ブランド毀損といったリスクを抑えながら、AIの生産性向上や新規価値創出を最大化するための土台です。
生成AIの普及と規制強化が進む現在、ポリシー未整備は機密情報の拡散や法的責任の発生など深刻な損失を招く恐れがあります。
策定にあたっては「目的とKPIの設定」「適用範囲の明確化」「データ取扱いルール」「禁止事項と例外手続き」「教育・監査体制」の5つの要素を押さえましょう。
そのうえで次の6つのステップで進めると、実務に根ざしたポリシーを短期間で整備できます。
- 現状把握
- リスクアセスメント
- ドラフト作成
- ステークホルダーレビュー
- 周知・教育
- 改善サイクル
マイクロソフトやNTTなど先進企業は、理念・仕組み・実務の三層構造やリスクベースのチェックリストを取り入れ、透明性と安全性を両立させています。
自社で策定する際は、こうした事例をベンチマークしつつ、自社の事業特性や規制環境に合わせて項目を具体化することが重要です。
AI活用を競争優位につなげるには、まず小規模でもよいのでポリシーを形にし、定期的なアップデートを組み込む仕組みを用意することが最短ルートです。
まだ準備が進んでいない場合は、本記事のチェックリストを参考に、今日から策定プロジェクトをスタートしてみてはいかがでしょうか。
生成AIサービス20選を一覧で比較(2025年版)
生成AIは日々のアップデートが急速で、ChatGPT、Claude、Gemini以外に業務特化の専門的な生成AIも増えてきました。
今回、今注目しておくべき生成AIツールを用途別に20個選出し、一覧表にまとめた資料をご用意しました。
サービス名・提供企業料金・AIごとの特徴・セキュリティ・利用されている分野など、一覧で比較できます。
- 導入検討の初期段階で候補を絞るとき
- 特定業務に適したツールを比較・整理するとき
- アップデートが追えていないので、一次整理を短縮したい
- 社内説明や稟議の補助資料として利用するとき
など、目的に応じてご活用ください。
特にChatGPT、Calude、Geminiについては種別(ROI改善や工数削減、リスク低減など)の導入効果事例をまとめており、利用シーンに応じた判断の補助として活用できるよう構成されています。
無料で取得できますので、ぜひお手元にダウンロードしてみてください。


コメント