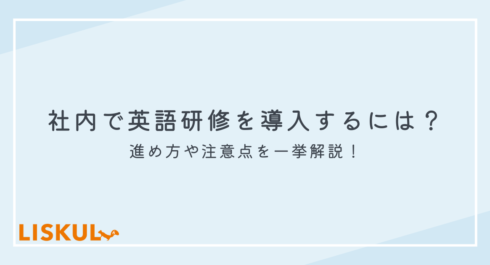
社内英語研修とは、社員が英語を学ぶための研修を企業内部で実施する取り組みのことです。
海外とのやりとりやグローバル展開の機会が増える中、社員一人ひとりの英語力を高めることは、業務効率の向上や組織全体の国際対応力の強化につながると期待されています。
しかし、社内で英語研修を導入するには、目的や対象者に応じた設計、運用体制の構築、社員のモチベーション維持といった多くの要素を考慮する必要があり、準備不足のままでは効果が得られない可能性もあります。
そこで本記事では、英語研修の導入背景やメリット・デメリット、導入手順、成功のためのポイント、注意点や課題までを一挙に解説します。
社内で英語研修を始めようとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
社員の英語力を効率よく伸ばすオンラインでできる英会話「DMM英会話法人向けサービス」
目次
※本記事は合同会社DMM.com提供によるスポンサード・コンテンツです。
英語を習得するための社内研修が注目されている
グローバル展開を視野に入れる企業が増える中、社員の英語力を底上げするために「社内英語研修」を導入する企業が急増しています。
海外との取引や海外支社との連携が当たり前になる今、英語力の有無がビジネス機会の拡大や業務効率に直結するケースも増えてきています。英語教育は一部の社員だけの課題ではなく、組織全体の競争力に関わるテーマです。
社内英語研修は、業務に直結する表現や専門用語を学べる点や、社員同士で切磋琢磨できる環境が構築できる点など、個人任せの語学学習では得にくいメリットがあります。
さらに、リスキリングの一環として取り入れることで、社員のキャリア支援やモチベーション向上にもつながるため、人材開発の観点からも注目されています。
一方で、研修内容や運用体制を誤ると、社員の負担感や研修効果のばらつきといった課題も生まれがちです。
参考:リスキリングとは?言葉の意味と8つの事例から学ぶ推進のコツ|LISKUL
次章では、社内で英語研修を行うことによって得られる具体的なメリットを詳しく解説していきます。
社内で英語研修を行うメリット4つ
社内で英語研修を実施することは、社員の語学力を高めるだけではなく、企業全体の国際対応力や組織文化の強化にも寄与します。
単なるスキルアップにとどまらず、人材育成や業務効率の向上、グローバル人材の確保といったさまざまな効果が期待できます。
1.実務に直結した英語力を習得できる
市販の教材や外部スクールでは学びにくい、自社特有の業務内容に合わせた英語力を習得できる点は、社内研修の大きな魅力です。
たとえば、製造業であれば技術マニュアルや設計書の読み書き、商社であれば商談や契約書対応など、現場に即した内容にカスタマイズすることで、学習効果を実務に直結させることができます。
また、社内の実際のメールやプレゼン資料を教材として使うこともでき、よりリアルな場面を想定したトレーニングが可能になります。
2.社員同士で学ぶことで継続しやすくなる
語学学習は継続が難しいという声が多い中で、社内研修は「仲間と一緒に取り組む」という環境が継続のモチベーションになります。
部署を越えて一緒に学ぶことで、コミュニケーションの活性化にもつながり、組織全体の一体感の醸成にも寄与します。
また、進捗の共有や成果発表の機会を設けることで、目標に対する意識が高まり、成果も見えやすくなります。
3.企業のグローバル対応力が高まる
英語対応できる社員が増えることで、海外取引や海外支社との連携をよりスムーズに行えるようになります。特定の人材だけに英語業務が集中する状況を避け、組織としてのグローバル耐性を高めることができます。
また、英語対応を前提としたプロジェクトにも柔軟に取り組めるようになり、結果として新たな市場開拓やパートナーシップの可能性も広がります。
4.社員のキャリア形成支援につながる
英語スキルは今後のキャリア形成においても武器となる要素です。社内研修として英語学習の機会を提供することで、社員の「成長支援」や「リスキリング」の一環となり、エンゲージメント向上にもつながります。
企業が社員のスキルアップを後押しする姿勢を見せることで、離職防止や人材の定着にも好影響をもたらします。
このように、社内英語研修は個人の語学力向上だけでなく、組織全体の生産性や競争力を高める多面的なメリットがあります。
一方で、すべての企業にとって万能な手法というわけではなく、デメリットやリスクも存在します。次章では、社内で英語研修を行う際に注意すべき主なデメリットについて詳しく見ていきましょう。
社内で英語研修を行うデメリット4つ
社内英語研修は多くのメリットがある一方で、導入や運用においていくつかの注意点や課題も存在します。
効果を最大限に引き出すためには、事前に想定されるデメリットを把握し、それらへの対策を講じておくことが重要です。
1.研修の継続が難しい場合がある
社内業務と並行して学習を行う必要があるため、時間の確保が難しくなりがちです。特に繁忙期などは学習の優先順位が下がり、参加率が低下することもあります。最初はモチベーションが高くても、日常業務に追われるうちにフェードアウトしてしまう社員も少なくありません。
このような状況が続くと、「制度が形骸化してしまう」というリスクがあり、結果的に会社の投資が無駄になる可能性もあります。
2.すべての社員に効果があるわけではない
社員の英語レベルや業務内容は多種多様であるため、画一的なカリキュラムでは効果が出にくいケースもあります。
たとえば、英語初心者と上級者が同じクラスで学んでしまうと、どちらにとっても学習効率が悪くなり、満足度が下がる恐れがあります。
また、日常的に英語を使わない部署では、学習の必要性を感じにくく、参加そのものが低調になることも考えられます。
3.運営負荷やコストがかかる
社内で英語研修を継続的に実施するには、講師の手配、カリキュラムの調整、教材準備、進捗管理など、多くのリソースが必要となります。外部の研修サービスを活用する場合でも、費用対効果を検証しながら継続することが求められます。
特に中小企業の場合、研修にかかる予算や担当者の時間確保が難しく、思ったように制度を回せないという悩みも少なくありません。
4.研修後の実務活用につながらないリスク
英語を学んでも、実際の業務で使う機会がない場合、せっかく身につけたスキルも徐々に忘れられてしまいます。「学んで終わり」「テストのための学習」に陥ると、本人の成長実感が得られず、企業側としても投資に対するリターンを得にくくなります。
英語研修は、実際の業務とどう結びつけるかまで設計しなければ、形だけの制度になってしまうおそれがあります。
こうしたデメリットも、あらかじめ把握して適切な対策を講じておけば、多くは回避可能です。
次章では、社内英語研修を実際に導入する方法について、ステップごとにわかりやすく解説していきます。導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
社内で英語研修を導入する方法5ステップ
社内英語研修を導入する際には、ただ外部サービスを契約するだけでは効果が出にくく、目的や対象、運用体制まで含めた戦略的な設計が求められます。特に実務での定着を目指す場合、事前準備や社内の巻き込み方が成否を大きく左右します。ここでは、英語研修導入の基本的なステップを紹介します。
1.研修の目的とゴールを明確にする
最初に取り組むべきは「なぜ英語研修を行うのか」という目的の言語化です。目的が曖昧なままスタートすると、受講者のモチベーションが上がらず、研修自体が形骸化する恐れがあります。
たとえば、以下のように具体的な目標を設定すると設計の方向性が定まりやすくなります。
- 海外支社とのWeb会議を日本側でも主導できるようにしたい
- 英文契約書を読める人材を増やしたい
- 新卒社員に基礎的な英語力を身につけさせたい
- グローバル展開に向けた管理職の英語力を強化したい
また、目標は定性的なものだけでなく、「TOEICで700点以上取得者を●人育成」「半年以内に英語メール対応を任せられる人材を●名輩出」など、数値指標を設定することで、研修後の効果測定も容易になります。
2.対象者を選定し、ニーズを把握する
誰を対象に実施するのかを明確にすることで、研修設計の精度が高まります。たとえば以下のようなパターンがあります。
- 全社員を対象にした基礎力強化型(社内公用語化を視野に)
- 海外出張・駐在候補者向けの実践英語特化型
- 管理職・マネージャー層向けのビジネス会話強化型
- 新卒・若手社員向けのキャリア支援型
対象者が決まったら、アンケートやヒアリングを実施して「今どのような英語スキルが必要とされているか」「どこに苦手意識があるか」を把握しましょう。
たとえば、営業部門ではスピーキングが、管理部門ではライティングやリーディングが求められるなど、職種ごとに優先度が異なる場合があります。
3.研修形式と実施体制を検討する
英語研修にはさまざまな形式があり、企業規模や予算、受講者の働き方によって適切なスタイルは異なります。以下のような形式があります。
- 集合研修(対面型):参加者同士のコミュニケーションが活発になりやすい
- オンライン研修:リモートワーク環境でも実施しやすく、時間の柔軟性がある
- オンデマンド型eラーニング:個人のペースで学習可能で、大規模展開に適している
- 個別英会話レッスン:中級〜上級者向けのアウトプット強化に最適
また、外部の語学研修サービスを利用する場合は、導入企業の実績、カスタマイズ性、サポート体制、料金体系などを比較検討しましょう。
参考:社内研修とは?知識・スキルが定着する設計方法と対象者別のテーマ例を紹介|LISKUL
オンライン研修とは? メリットや必要な環境・サービス を分かりやすくご紹介|LISKUL
eラーニングとは?意味や特徴、研修との違い、サービス検討のポイント|LISKUL
4.カリキュラム・教材を自社に合わせて設計する
汎用的な英語研修ではなく、できるだけ実務に寄せた内容にすることで、受講者の納得感と実用性が高まります。たとえば以下のような工夫が効果的です。
- 社内資料(マニュアル、報告書、メール)をもとに教材を作成
- 自社業界に特化した用語や事例を取り入れる
- 業務フローやロールプレイを英語で再現する(会議進行、顧客対応など)
たとえば、グローバルに展開している製造業では「製品の構造を英語で説明する」「不具合の原因を技術的に説明する」といったロールプレイが非常に実践的で、好評を得ています。
5.評価指標とフォローアップ体制を整える
研修成果を可視化し、継続的に改善していくためには、事前・事後テストやTOEICの定期受験、英語での業務実績(例:海外メールの送信数、Web会議での発言回数など)など、具体的な評価指標を用意しておくことが重要です。
さらに、研修後のフォローも忘れてはいけません。たとえば以下のような仕組みが有効です。
- 月1回の英語プレゼン大会を実施
- 成果発表会を設けてモチベーションを可視化
- 社内イントラネット上に学習リソースを公開
- 英語力を評価項目に反映し、処遇と連動させる
このように、英語研修の導入は「誰に」「何を」「どうやって」「いつまでに」という4つの視点を明確にすることが成功の鍵です。目的と実務の両方に結びついた設計を行うことで、英語力の向上だけでなく、組織全体の成長にも寄与する施策へと発展させることができます。
次章では、こうした研修をより効果的に進めるために欠かせない「成功に導く運用のポイント」について詳しく見ていきます。実施後の定着や成果を出すためのヒントを確認していきましょう。
社内の英語研修を成功させるポイント3つ
社内で英語研修を実施するだけでは、必ずしも成果につながるとは限りません。研修の効果を最大化し、受講者の満足度や実務への定着を高めるには、運用面での工夫が不可欠です。ここでは、研修を成功させるために意識したい主なポイントを3つ紹介します。
1.経営層・管理職の理解と協力を得る
英語研修を単なる「学習支援」としてではなく、「経営戦略の一環」として捉えてもらうことが重要です。経営層や管理職が制度の意義を理解し、自らが研修を推奨したり受講者をサポートする体制をつくることで、現場の協力も得やすくなります。
たとえば、管理職が英語での会議を一部取り入れたり、研修成果を定例会議で発表する場を設けるなど、実務に引き寄せる仕掛けも効果的です。
2.学びを業務で使う機会をつくる
英語力は「使わなければ定着しない」スキルです。学んだ内容を業務で活かせるよう、英語メールのやりとり、簡単な英語ミーティング、社内発表の英語化など、実践の場を用意しましょう。
実際に使って成功体験を積むことで、自信が生まれ、学習意欲も継続しやすくなります。
3.モチベーション維持の仕組みをつくる
語学学習は長期的な取り組みになるため、受講者のモチベーションをどう保つかが重要です。定期的な成果発表会、学習進捗の見える化、評価への反映など、達成感や周囲のフィードバックが得られる仕組みを取り入れましょう。
また、表彰制度やポイント制度を導入して、小さな成功に対する報酬を設定するのも効果的です。
社内の英語研修は、制度を導入するだけではなく、社員の学習意欲や実務活用をどう促すかが成否を左右します。
次章では、導入や運用時に特に注意しておきたい具体的なリスクや注意点を詳しく見ていきます。
導入の際に注意すべき5つのポイント
社内英語研修は、導入するだけでも一定の効果が期待されますが、無計画に始めてしまうと時間やコストばかりがかかり、形骸化してしまうリスクもあります。ここでは、導入時に特に注意しておきたい5つのポイントを解説します。
1.目的が曖昧なまま始めない
社内英語研修は、目的が曖昧なまま始めると失敗しやすくなります。「とりあえず始めてみる」という導入では、参加者のモチベーションが高まらず、研修が形だけで終わってしまう可能性があります。
そのため、研修の目的(例:海外拠点との会議対応、英文メール対応の強化など)とゴールを明確に設定し、「なぜこの研修が必要なのか」を受講者に丁寧に伝えることが重要です。
2.受講者のレベル差に配慮する
受講者のレベル差に配慮しない研修は、満足度と効果を下げる原因です。英語力には個人差が大きく、一律のカリキュラムでは理解度や習得スピードに偏りが生じやすくなります。
初級者・中級者・上級者でクラスを分ける、もしくは個別対応可能なカリキュラムを選ぶなど、柔軟な設計が求められます。
3.業務への影響を最小限に抑える
業務と並行して実施する英語研修は、参加率や集中度に影響を及ぼす可能性があります。「業務の合間での受講が負担になる」「片手間になってしまう」といった事態を避けるためには、無理のないスケジュール設計が重要です。
スケジュールや業務調整については事前にマネージャーと連携し、無理のない運用体制を整えましょう。
4.講師や教材の質を見極める
英語の講師や教材の選定は、研修の満足度と成果に直結します。
講師が単にネイティブであるだけでは不十分で、ビジネス英語や日本企業の文化に理解のある人材を選ぶことが重要です。
教材も汎用的なものではなく、可能であれば自社業務に沿った内容を取り入れることが望まれます。
5.評価とフィードバックの仕組みを設ける
「受けっぱなし」で終わる研修は定着しづらく、成果も見えにくくなります。研修中の進捗や理解度を確認できる仕組みや、受講後のアンケート・レビュー・成果報告を取り入れることで、改善のサイクルを回すことができます。
これらのポイントをあらかじめ把握し、適切な対策を講じておくことで、英語研修の導入をスムーズに進めることができます。
次章では、実際に運用していく中でよくある課題とその具体的な対処法を紹介します。想定外の事態にも柔軟に対応できるよう、事前に備えておきましょう。
よくある課題と対策4つ
社内で英語研修を導入しても、すべてが順調に進むとは限りません。多くの企業が、研修の定着や効果測定、モチベーション維持などに関する課題に直面します。ここでは、実際によくある課題とその具体的な対処法を紹介します。
課題1:参加率が下がる・途中離脱が増える
最初は意欲的に参加していた社員が、業務の繁忙やモチベーション低下によって離脱してしまうケースはよく見られます。
- 定期的に参加者の状況をチェックし、個別フォローを実施する
- 研修スケジュールを業務とバッティングしない時間帯に設定する(例:昼休み前後や就業時間内)
- 成果発表会や修了証など、目標や区切りを明確にして達成感を得られるようにする
課題2:実務に活かされない
学習内容が業務と直結していないと、学んだことが現場で活かされず、本人も「学ぶ意味がない」と感じてしまいます。
- 研修内容を自社の業務に即したものにカスタマイズする(例:実際の英文メールや資料を使う)
- 英語を使う機会を業務の中に組み込む(例:簡単な日報や朝礼を英語で実施)
- 受講後に「英語で○○してみた」体験を共有する場を作る
課題3:レベル差が大きく、一律の内容では対応できない
英語スキルには個人差があるため、研修の内容が簡単すぎる、または難しすぎるという不満が生じやすくなります。
- レベル別のクラス分けや、eラーニングとの組み合わせで柔軟に対応する
- 自己学習+グループレッスンのハイブリッド形式を採用する
- 初回にプレイスメントテストを行い、最適なレベルで受講開始できるようにする
課題4:成果が見えにくく、効果を判断しにくい
英語力は短期間で大きく向上するものではないため、効果が感じられず、研修の継続に迷いが生じることがあります。
- 定期的にTOEICなどのテストを実施し、数値としての変化を追う
- 実務上で英語を使った経験の数(例:メール送信数、会議参加数など)をKPIとして活用する
- 上司や人事によるフィードバックを評価プロセスに組み込むことで、主観だけでなく客観的な成果も可視化する
このような課題は、あらかじめ対策を講じておくことで大きな問題に発展するのを防げます。運用中に柔軟に改善できる体制を整えておくことが、英語研修の継続的な成功につながります。
次章では、英語研修を実施する上で生まれやすい誤解や勘違いを紹介します。
よくある誤解4つ
最後に、社内で英語研修を実施する際のよくある誤解を4つ紹介します。
誤解1:英語が得意な人だけが受けるべきもの
英語研修というと、もともと英語が得意な人や海外案件に関わる人だけが対象だと思われがちですが、それは大きな誤解です。実際には、初級者から中級者を対象とした基礎力の底上げこそが社内研修の主な目的であり、英語に自信がない人ほど受ける価値があります。
社員全体のスキルレベルを引き上げることが、長期的には企業の国際対応力の強化にもつながります。
誤解2:TOEICスコアが上がればそれで成功
英語研修の成果を測るためにTOEICスコアを指標にすることは一般的ですが、それだけで研修の価値を判断するのは危険です。スコアが上がったとしても、実際の業務で英語を使えていなければ意味がなく、逆にスコアがさほど伸びていなくても、英語での会議発言やメール対応が増えていれば十分に実践的な効果が出ていると言えます。
数値評価と実務貢献の両面で成果を捉えることが大切です。
誤解3:一度導入すればあとは自動的に回る
制度やカリキュラムを整えて研修を始めれば、あとは自然に回っていくと思われがちですが、実際はそう簡単ではありません。参加率の低下やモチベーションのばらつき、業務との両立の難しさなど、運用フェーズでの課題は必ず発生します。
継続的な運用改善と社内のサポート体制がなければ、制度は徐々に形骸化してしまいます。
誤解4:英語研修は一部のグローバル企業だけの取り組み
海外に拠点がある企業や外資系企業だけが英語研修を行うものだと考えているケースもありますが、近年では中小企業や地域密着型の企業でも、英語力強化への取り組みが広がっています。
外国人顧客への対応や越境EC、海外とのオンライン取引など、企業規模を問わず英語スキルの重要性が増しており、社内英語研修は今や多くの業種・業態で有効な施策となっています。
まとめ
本記事では、英語研修の社内導入に関する背景やメリット・デメリット、具体的な導入方法、成功のポイント、注意点や課題への対処法まで一挙に解説しました。
社内英語研修とは、社員の語学力を高めることで、国際的な業務対応力を強化し、組織全体の競争力を向上させるための取り組みです。
実務に即した英語力の習得、社員間の学習意欲の向上、企業のグローバル対応力の強化など、社内で実施するからこそ得られる多くのメリットがあります。
一方で、研修の継続性やレベル差、業務との両立、実務への定着といった課題もあり、明確な目的設定や適切な運用設計が求められます。成功のためには、受講者のニーズに合わせた柔軟なカリキュラム設計や、社内の巻き込み、モチベーション維持の工夫が不可欠です。
社内英語研修を検討する際は、単なる語学研修として捉えるのではなく、社員のキャリア支援や企業の持続的な成長につながる投資として設計・運用することが重要です。
グローバル化が進む今、英語研修の導入は企業の未来を支える一手となります。英語力を組織の強みに変えたいと考えている方は、導入を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
社員の英語力を効率よく伸ばすオンラインでできる英会話「DMM英会話法人向けサービス」
※本記事は合同会社DMM.com提供によるスポンサード・コンテンツです。
コメント