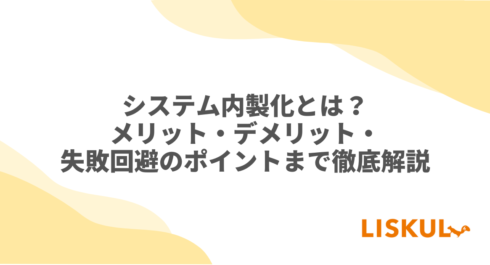
システム内製化とは、社内のリソースを活用して業務システムを自社で開発・運用する取り組みのことです。
外注に頼らず、スピーディかつ柔軟に改善を行えることから、変化の激しいビジネス環境において注目を集めています。現場の声を反映したシステム設計がしやすくなるほか、社内にITノウハウが蓄積され、継続的な改善が可能になるというメリットもあります。
一方で、エンジニア人材の確保や、体制構築にかかるコスト、属人化による運用リスクなど、慎重に対応すべき課題も多く存在します。
そこで本記事では、システム内製化の基本的な考え方から、注目される背景、メリット・デメリット、成功に導く判断基準、具体的な進め方まで一挙に解説します。
自社のIT活用に課題を感じている方や、内製化の可能性を探りたいと考えている方は、ぜひご覧ください。
【システム内製化に欠かせない】エンジニアを正しく評価し採用する方法
目次
※本記事は株式会社ギブリー提供によるスポンサード・コンテンツです。
システム内製化とは
システム内製化とは、自社内のリソースを使って業務システムやITツールの企画・開発・運用を行う取り組みを指します。従来はシステム開発の多くを外部のベンダーに委託するケースが主流でしたが、近年は自社で開発体制を整える企業が増えています。
この動きの背景には、業務のデジタル化が進むなかで「スピード感」や「柔軟性」が重視されるようになったことがあります。外部に依頼すると、要件定義から実装、改修に至るまで多くの調整が必要となり、変化への対応が遅れるケースも少なくありません。
一方、内製であれば、現場の声を素早く反映し、必要な機能を迅速に追加・改善できます。
また内製化は単なる開発手段ではなく、ITを競争優位に変える戦略的な手段として位置づけられるようになってきました。開発だけでなく、業務理解やユーザー視点を持つ社内人材がシステム設計に関与することで、より実践的で効果的な仕組みを作れる点も評価されています。
ただし、内製化はすべての企業に適しているわけではなく、体制づくりや人材確保が前提となります。次章では、こうした内製化が注目を集めている背景について詳しく見ていきます。
システム内製化が注目される背景にある4つの要因
業務の複雑化や変化の激しさに対応するため、システムを自社で柔軟に設計・運用できる体制へのニーズが高まり、内製化が注目を集めています。
従来は外部ベンダーへの委託が一般的でしたが、スピードや柔軟性の観点から、自社内で開発・改善を行う「内製型」の取り組みが再評価されています。IT人材の確保や技術の進化も、こうした動きを後押ししています。
1.外注依存では変化への対応が遅れる
市場や顧客ニーズが短期間で変化するなかで、外部に依頼してから要件定義・開発・リリースまでに時間がかかることが課題となっています。その点、内製化であれば社内の意志決定を素早く反映し、スピーディな対応が可能になります。
2.ノーコードやクラウドの普及でハードルが下がった
ノーコードやクラウドの普及により、システムの内製化に取り組むハードルが下がったことも要因の1つです。
従来は、社内でシステムを開発・運用するには高度なプログラミングスキルを持つエンジニアが必要で、中小企業や非IT部門では実現が難しい状況でした。
現在はノーコード・ローコードツールが広まり、業務部門のメンバーでも開発や運用に関わりやすくなっています。
さらに、クラウドサービスの活用により、インフラ構築やメンテナンスの手間も軽減され、少人数でも柔軟なシステム対応が可能です。
3.外部委託のリスクを避けたい企業が増加
外注先にノウハウが蓄積され、自社ではブラックボックス化してしまうリスクを回避したいという企業も増えています。
特に長期的なIT戦略を考えるうえで、システムの設計思想や運用ノウハウを社内に残すことは大きな意味を持ちます。
4.競争優位の源泉としてITを活用したい
企業にとってITは「守りのコスト」ではなく「攻めの武器」として位置づけられるようになってきました。内製化を通じて業務にフィットしたシステムを柔軟に作り込み、改善を繰り返すことで、競合との差別化につながるという考え方が広がっています。
以上のように、複数の要因が重なり、システム内製化は単なる流行ではなく戦略的な選択肢として注目されています。
続く章では、内製化が注目されていても失敗リスクがある点について確認していきましょう。
システム内製化は失敗することもあるので注意が必要
システム内製化は大きなメリットをもたらす一方で、計画や体制が不十分なまま進めると失敗に陥るリスクもあります。
外注に比べて柔軟性があるといわれる内製化ですが、全ての企業にとって適しているとは限りません。人材確保、スキル育成、プロジェクトマネジメントなど、複数の要素がかみ合って初めて成果につながります。
ここでは、内製化でよく見られる4つの失敗パターンを解説します。
1.人材不足のまま内製化を進めてしまう
社内に十分な開発経験や技術的知見がないままプロジェクトをスタートさせると、開発が滞ったり、品質が担保されないままリリースしてしまう恐れがあります。
外注のような専門サポートがないため、特に立ち上げ期はスキルのある人材の確保がカギとなります。
2.「内製すること」自体が目的化してしまう
本来、内製化は業務改善や競争力向上といった目的を実現する手段に過ぎません。
しかし、「外注コストを削減したい」「内製化がトレンドだから」といった理由で目的が曖昧なまま進めてしまうと、実用性の低いシステムが出来上がってしまうこともあります。
3.属人化により運用がブラックボックス化する
特定の社員に開発や運用のノウハウが集中すると、退職や異動があった際にシステム維持が困難になります。
ドキュメント不足や引き継ぎの不備は、内製化の柔軟性を損なう大きな要因となります。
4.社内の巻き込みが不十分で現場が使いこなせない
現場ニーズのヒアリングやフィードバックを反映せずに開発を進めると、実際の業務とかみ合わないシステムになるケースがあります。
技術サイドだけで完結するのではなく、業務部門との連携も内製化の成功に不可欠です。
このような失敗を回避するためには、内製化に取り組む前に「判断基準」を持つことが重要です。次章では、内製化の適否を見極めるためのポイントを解説します。
システム内製化のメリット4つ
システム内製化には、スピード・柔軟性・ノウハウの蓄積といった外注では得がたい多くのメリットがあります。
自社内で開発・運用することで、変化に迅速に対応できるだけでなく、業務理解を深めたうえで改善を進められるため、ビジネスの成果にも直結しやすくなります。
ここでは、代表的なメリットを4つ紹介します。
1.要望の反映が早く、改善サイクルを回しやすい
内製であれば、現場からのフィードバックをすぐに開発チームに伝えられます。改修や機能追加を素早く行えるため、業務の改善スピードが格段に向上します。
仕様変更が発生しても、外注のような契約変更や追加費用の手間が少ない点も魅力です。
2.自社の業務にフィットしたシステムを構築できる
システム開発を内製化することで、自社の業務に最適化されたシステムを構築できます。自社の業務や運用を深く理解している担当者が開発を主導するため、実務に即した設計がしやすくなります。
外部ベンダーに依頼する場合は、業務内容の理解に限界があり、要件のすり合わせに時間や手間がかかることもあります。
その点、内製化であれば現場に馴染みやすく、スムーズに運用へ移行できるシステムを実現しやすくなります。
3.ノウハウが社内に蓄積される
システム開発を内製化することで、開発や運用に関するノウハウを社内に蓄積できます。
自社で知識を持つ人材が増えることで、継続的な改善や保守を自立的に進められるようになります。
属人化に注意しながら組織的にノウハウを共有すれば、システム全体の活用力を底上げすることも可能です。
結果として、外部に依存せずに柔軟かつ持続的な運用体制を構築できます。
4.外注コストの削減につながる可能性がある
システム開発を内製化することで、長期的には外注コストを削減できる可能性があります。
特に繰り返し発生する改修作業や日常的なメンテナンスを社内で対応できるようになれば、外部ベンダーへの依頼頻度が減り、ランニングコストの最適化が期待できます。
一時的な開発リソースの確保に比べ、継続的な費用負担を抑えることができる点は大きなメリットです。
参考:コスト削減とは?実施手順と成功させるための3つのポイント|LISKUL
このように、システム内製化は業務とITを密接に連携させるうえで非常に有効な手段です。
次章では、反対に内製化に伴う課題や注意点について解説します。
システム内製化のデメリット4つ
システム内製化には多くの利点がありますが、人材不足や運用体制の不備など、導入・継続には一定のハードルがあります。
成功させるには、リスクやコスト、組織面での課題もあらかじめ理解しておく必要があります。
1.技術者の確保・育成が難しい
内製化の最大の課題は、ITスキルを持つ人材の確保と育成が難しいことです。
システム開発や運用には専門知識を持つエンジニアが不可欠ですが、現在は採用競争が激しく、必要な人材を採用するのは容易ではありません。
仮に採用できた場合でも、実務に対応できるまでの育成や、定着支援の仕組みがなければ戦力として継続的に活用することは困難です。
そのため、人材戦略を中長期的に計画する必要があります。
2.初期コストや負担が大きくなりやすい
内製化を進めるには、初期コストや人的な負担が大きくなりやすいという課題があります。
開発環境の構築や人件費、教育研修などに投資が必要となり、導入初期はコストがかさむ傾向にあります。
内製化をゼロから始める場合は、短期的なROI(投資対効果)を出すことが難しく、社内での理解と協力を得るための説明も求められます。
これらの負担を適切に見積もったうえで、段階的に進めることが重要です。
3.属人化・ブラックボックス化のリスク
内製化によって、属人化やブラックボックス化が進むリスクがあります。
開発や運用に関する知識が特定の担当者に偏ってしまうと、その人の退職や異動によって業務が停滞する恐れがあります。
また、ドキュメントが不十分だったり、ナレッジの共有が行われていなかったりすると、組織としてのシステム運用能力が低下します。
こうしたリスクを防ぐためには、情報の共有や引き継ぎ体制の整備が不可欠です。
4.セキュリティや運用の専門知識が求められる
内製化には、開発スキルだけでなく、セキュリティや運用に関する専門知識も求められます。
特にクラウド環境の構築やユーザー認証、インフラ管理などに関する知識が不足していると、セキュリティリスクを見落とす可能性があります。
また、トラブル対応や継続的な保守にも一定の経験と体制が必要です。専門知識を持つ人材を確保し、継続的なスキルアップを支援する仕組みづくりが求められます。
このように、内製化には注意すべき点も多く存在します。ただし、こうしたデメリットは、事前の判断基準を明確にすることである程度コントロールできます。
次章では、内製化に踏み切る前に検討すべきポイントを整理します。
内製化を成功させるための5つの判断基準
内製化の成否は目的、スコープ、リソース、社内体制などを事前に整理し、自社にとって現実的かつ効果的な内製化の形を見極めることが重要です。
勢いや流行だけでスタートすると、途中で頓挫したり、かえって非効率になるケースもあります。
自社にとって「今、本当に内製すべきか」を判断するための基準を明確に持つことが大切です。
1.内製化の目的が明確になっているか
内製化の可否を判断するうえで、まず目的の明確化が不可欠です。「なぜ内製化するのか?」が曖昧なまま進めると、途中で方針がぶれる可能性があります。
コスト削減、スピード向上、業務にフィットした改善の実現など、内製化によって何を達成したいのかを具体的に設定することが第一歩です。
2.内製する対象・スコープが適切か
内製すべき領域を見極めることが、成功の前提となります。
すべてのシステムを内製する必要はありません。業務に直結し競争力に関わる部分は内製し、基幹系や共通業務系などは外注または既存サービスを活用する、といった判断も有効です。リソースの集中配分を考慮しましょう。
3.自社に必要な技術・人材が揃っているか
内製化には、必要なスキルと人材の確保が前提となります。
現時点でどの程度の開発・運用能力があるのか、どの分野に外部支援が必要なのかを把握することが重要です。完全な自社内製ではなく、初期は外部パートナーのサポートを受けながら段階的に移行する形も現実的です。
4.経営層・現場双方の理解と協力があるか
内製化はIT部門だけの取り組みではなく、組織全体の協力が必要です。
経営層の理解と投資判断、現場のニーズと開発のすり合わせがうまく連携できていなければ、成果は出づらくなります。
5.中長期で運用していける体制があるか
内製化は一度導入して終わりではなく、継続的な運用・改善が求められます。
中長期で組織として内製チームを育成・維持できる見通しが立てられるかも、重要な判断基準となります。
これらの基準をもとに、自社にとって最適な内製化の形を見定めることが成功への近道です。
次章では、実際にシステムを内製化していくための具体的なステップをご紹介します。
システム内製化の進め方6ステップ
システム内製化を成功させるには、「段階的に」「スモールスタートで」「外部リソースも柔軟に使いながら」進めることがポイントです。
最初からすべてを内製するのではなく、自社にとって無理のない範囲から始め、試行錯誤を重ねながら体制を整備していくのが現実的なアプローチです。
ステップ1:業務とシステムの現状を棚卸しする
まずは、現時点で自社が利用しているシステムや業務フローを可視化しましょう。
たとえば「販売管理」「問い合わせ管理」「勤怠管理」など、業務ごとの使用ツールや課題を洗い出し、どこに内製化の余地があるかを見極めます。
・営業部門で使っているSFA(営業支援ツール)が現場に合っていないなら、「最初はスプレッドシート+GAS(GoogleAppsScript)で試作」→「実用化」→「ノーコードツールでの置き換え」など段階的な検証が可能です。
ステップ2:小規模なプロジェクトから試す(スモールスタート)
まずは「限定された業務範囲」「1部門内で完結するシステム」など、小さな成功を積み上げていくことが重要です。
最初から基幹系システムなど大規模な領域を内製しようとすると、開発負荷も高く、失敗のリスクも大きくなります。
経理部門の「経費精算申請」をGoogleフォーム+自動スプレッドシート連携で内製し、業務効率化を実感→他部門にも展開、のように小さな改善から効果を可視化していくと、社内の理解も得られやすくなります。
ステップ3:内製チームを段階的に構築する
内製化の鍵となるのは、実行するチームです。必ずしも最初から専任の開発者を多く抱える必要はなく、現場にITに強い社員がいれば、そこからチームを組成することも可能です。
また、外部エンジニアとの協業も有効です。
・プロジェクトリーダー(社内推進担当)
・現場部門の代表(業務要件を整理)
・技術担当(開発・設計)
・必要に応じて外部アドバイザーやCTO代行
ノーコード・ローコードを活用する場合は、非エンジニアの業務担当が自らプロトタイプを作る形も増えてきています。
ステップ4:ツール・技術選定と開発環境の整備
内製化では、開発に使用する技術やツールの選定が重要です。最初からフルスクラッチ開発を目指すのではなく、業務内容やチームの技術レベルに合わせて以下のような選択肢を検討しましょう。
・ノーコード/ローコード:Kintone、Notion、Airtable、PowerApps
・内製支援サービス:GitHubCopilot、ChatGPT、StackOverflow
・開発フレームワーク:Laravel、React、Firebaseなど
ツール選定の段階で、保守・拡張のしやすさやセキュリティの観点も踏まえて検討することが必要です。
ステップ5:運用を見据えて仕組み化する
開発したシステムを長く使っていくためには、属人化を防ぎ、運用が安定するような仕組みづくりが必要です。コードや仕様のドキュメント化、マニュアルの整備、ナレッジの共有といった地道な取り組みが、持続的な内製化体制につながります。
また、「開発したら終わり」ではなく、リリース後に使い勝手を検証し、フィードバックをもとに改善するループ(PDCA)を組み込むことが重要です。
参考:PDCAとは?具体例、OODAとの違い、実践方法を一挙解説!|LISKUL
ステップ6:段階的に対象範囲を広げる
最初の成功体験をもとに、次は他部門や別業務へと内製の対象を拡大していきます。その際、共通機能やUI設計の統一などを意識することで、全体最適の視点を持ちやすくなります。
また、すべてを自社で完結させる必要はなく、「コア部分は内製、周辺や保守は外部に委託」といったハイブリッド型も現実的な選択肢です。
このように、システム内製化は「一気に進める」のではなく、「業務の特性に応じて小さく始め、段階的に広げる」ことで、失敗リスクを抑えながら確実に成果を出すことが可能になります。
次章では、実際にありがちなシステム内製化に向いている企業の特徴を見ていきましょう。
システム内製化に向いている企業の特徴5つ
システム内製化がうまくいく企業には、共通して「スピード重視」「変化対応力」「ITへの前向きな姿勢」といった特徴があります。
すべての企業にとって内製化が最適というわけではありませんが、以下のような条件を満たしている場合、内製による業務改善や競争力強化の効果が見込めます。
- 変化のスピードが速い業界・ビジネスモデルである
- 現場が業務改善への関心を持っている
- 一定のITリテラシーや人材が社内に存在する
- 社内でノウハウを蓄積・共有しようとする文化がある
- 自社にしかない強みをシステムに反映させたい
1.変化のスピードが速い業界・ビジネスモデルである
ITやスタートアップ業界、Webサービス系など、環境変化が激しい業種では、要件変更や機能追加のスピードがビジネスの成否を左右します。
内製化により、意思決定と開発が直結し、柔軟な対応が可能になります。
2.現場が業務改善への関心を持っている
業務部門がシステムに対して前向きで、「こうすればもっとよくなる」というアイデアを持っている企業では、内製化が機能しやすくなります。現場と開発が連携しやすいため、使いやすいシステムが生まれやすい環境です。
3.一定のITリテラシーや人材が社内に存在する
エンジニアを雇用していなくても、ITに詳しい社員や業務改善に積極的な人材がいる企業では、ノーコードやローコードを起点に内製の一歩を踏み出すことが可能です。必要に応じて外部の支援を受ける柔軟性も重要です。
4.社内でノウハウを蓄積・共有しようとする文化がある
「人に頼るのではなく、仕組みで解決する」思考を持ち、ドキュメント化やナレッジ共有を重視する企業文化があると、属人化を防ぎ、内製化の効果を長期的に維持しやすくなります。
5.自社にしかない強みをシステムに反映させたい
業務プロセスが他社と大きく異なる場合、既製品のパッケージソフトでは対応しきれないことがあります。自社固有の強みをシステムに落とし込みたい場合には、内製化によるカスタマイズ性の高さが強力な武器になります。
以上のような特徴に当てはまる企業は、内製化を通じて自社の価値をさらに高める可能性があります。
続く章では、内製化をめぐってよくある勘違いを紹介します。
システム内製化に関するよくある誤解4つ
最後に、システム内製化に関するよくある誤解を4つ紹介します。
誤解1「内製化すればコストが必ず下がる」
短期的には、内製のほうが人件費や教育コストがかかる場合もあります。特に人材採用や環境整備に投資が必要な初期段階では、外注より高くつくことも珍しくありません。コスト削減は長期的な視点で判断する必要があります。
誤解2「エンジニアがいないと内製化は無理」
専門的なエンジニアがいない企業でも、ノーコード・ローコードツールや外部パートナーの活用により、段階的に内製を進めることは可能です。最初から全て自社で開発する必要はなく、「できる範囲から始める」姿勢が重要です。
誤解3「すべてのシステムを内製化すべき」
内製化はあくまで選択肢の一つであり、全ての領域に適しているわけではありません。たとえば、会計・人事・勤怠などの汎用業務はパッケージやSaaSを活用し、競争優位に直結する領域のみを内製する「ハイブリッド型」が効果的な場合も多くあります。
誤解4「内製化すれば外注は一切不要になる」
内製化を進めても、すべてを自社で完結する必要はありません。要件整理や初期設計だけ外部の支援を受けたり、技術アドバイザーを活用する形も選択肢の一つです。外注と内製のバランスを柔軟に調整することが、現実的な運用につながります。
まとめ
本記事では、システム内製化の基本的な考え方から、注目されている背景、メリット・デメリット、成功のための判断基準や具体的な進め方まで一挙に解説しました。
システム内製化とは、自社内でシステムを企画・開発・運用する体制を築く取り組みのことです。
外部依存から脱却し、変化に強い柔軟な組織を作る手段として、多くの企業で注目が高まっています。特に、業務改善のスピードや、現場ニーズに合ったシステム設計、社内へのノウハウ蓄積といった観点で、大きな効果が期待できます。
一方で、専門人材の確保や教育、継続的な運用体制の整備といった課題もあるため、自社の状況に応じた慎重な判断が必要です。内製化はすべての企業にとって万能な手段ではなく、段階的に取り組むことが成功の鍵となります。
自社にとって最適な進め方を見極めながら、まずはスモールスタートで業務に密着した部分からの内製化を検討してみてはいかがでしょうか。将来的には、内製化が企業の競争力を高める武器となるはずです。
国内導入社数No.1!エンジニアのスキルを正しく評価するエンジニア/DX人材のスキル可視化ツール『Track Test』(PR)
『Track Test』は、株式会社ギブリーが運営する導入社数No.1のエンジニア/DX人材のスキル可視化ツールです。
豊富な800問以上の問題を組み合わせることで、自社独自の技術課題を簡単に作成・配信します。候補者から提出されたソースコードを自動採点し、レビューをすることができます。
これまで職歴書や、数時間の面接だけではわかりづらかったエンジニア候補者の実務のスキルを可視化すると共に、選考プロセスにおけるスキル見極めのコストを削減することが可能です。
DX推進・デジタル組織の内製化をおこなう大手から、ベンチャー・スタートアップまで幅広い企業が、エンジニア採用・評価・育成のシーンにて、Track Testを活用。
累計350社以上の実績をもとに、Trackカスタマーサクセスチームが伴走しながら最適な技術選考のプロセス設計をサポートします。
詳細は下記サービス資料をダウンロードしてご確認ください。
国内導入社数No.1『Track Test』のサービス資料をダウンロードする<無料>
※本記事は株式会社ギブリー提供によるスポンサード・コンテンツです。

コメント