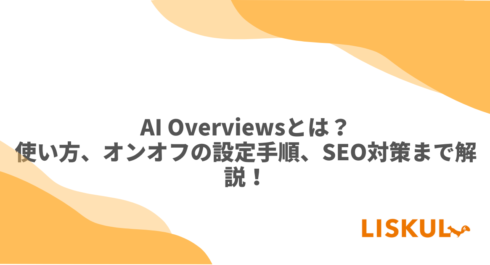
AI Overviewsとは、Google検索の最上部に生成AIが提示する要約スナップショット機能です。検索意図を瞬時に解析し、複数の情報源を統合した「ひと目で分かる答え」を表示することで、調査や意思決定にかかる時間を大幅に短縮できます。
この機能を活用すれば、社内リサーチや顧客提案の下調べを効率化できるほか、要約内のリンクから信頼性の高いページへ直接アクセスできるため、情報収集の精度も高められます。
一方で、生成AIゆえの誤情報リスクや、自社サイトへのオーガニック流入が減少する可能性など、注意すべき点も存在します。
そこで本記事では、AI Overviewsの仕組みや使い方、オンオフ設定の手順、メリットとデメリット、SEOへの影響と対策、要約への掲載を避ける方法までを網羅的に解説します。
AI Overviews時代の検索戦略を最適化したい方は、ぜひ最後までご一読ください。
【早見表】生成AIサービス主要20選(2025年版)【社内共有OK】
目次
AI Overviewsとは
AI Overviewsは、Google検索結果の最上部に生成AIが瞬時に作成した要約スナップショットを表示し、検索意図の核心をまず示したうえで、深掘りに役立つリンクを併置する新しい検索体験です。
2024年5月14日のGoogle I/Oで、試験機能「Search Generative Experience(SGE)」から正式版へと改称・一般提供が発表され、まず米国の英語検索に導入された後、段階的に地域と言語が拡大しています。
概要生成にはGeminiモデルが利用されており、クエリの意図を推定して複数のウェブページやナレッジグラフの情報を統合し、数秒で回答を提示する仕組みです。結果には出典ページがカード形式で提示されるため、利用者は要約を確認しながら信頼できるソースへ直接アクセスできます。
かつてはSearch Labs内のテスト版として提供されていましたが、正式公開後は「プラン生成」や「追加質問チップ」など、マルチステップの情報収集を前提にした機能も順次追加されており、複雑な調査や比較検討を行うビジネスシーンでの活用が進みつつあります。
AI Overviewsが登場した背景にある3つの要因
検索そのものを「探す」作業から「答えを得る」体験へ転換する。これがGoogleがAI Overviewsを投入した最大の狙いです。
情報洪水で意思決定に時間がかかるユーザの課題を解決するために、「最適な答えをすばやく提示できる検索」が求められ、生成AIの実用フェーズ入りとともに検索の在り方を再定義する必要が生じました。
1.検索ニーズの複雑化と情報過多
スマートフォンの普及で検索クエリは長文化・多段化し、比較検討や手順確認など“調べもの”の中身も多層的になりました。
結果、複数ページを行き来して断片情報を組み合わせる負荷が高まり、検索エンジン側には「まとめて要点を提示する」解決策が求められていました。
参考:ニーズとは?5分でわかるニーズの基礎とビジネスへの活用法|LISKUL
2.生成AI技術の急速な進化
大規模言語モデルが高精度な要約や推論を短時間で行えるようになり、検索クエリの意図を解釈して回答を生成する基盤が整いました。
Googleは自社モデルGeminiを検索アルゴリズムに統合し、リアルタイム検索インデックスとのハイブリッド処理で鮮度と信頼性の両立を図っています。
3.競合プラットフォームとユーザー獲得競争
OpenAIとMicrosoftがChatGPT/Copilot経由で検索トラフィックを奪い始めたことで、Googleは「検索の主戦場」が変わり得ると判断しました。
AI Overviewsは、既存検索の強み(膨大なインデックス・広告エコシステム)を生かしつつ、対話型AIの利便性を融合する防衛的かつ攻めの一手です。
4.“Helpful Content” ポリシーの延長線
Googleは近年EEATを軸に「役立つコンテンツ」を優遇してきましたが、AI Overviewsではその思想をさらに一歩進め、「役立つ回答を即時に生成する」方向に舵を切りました。
検索品質ガイドラインと生成AIの安全フィルターを組み合わせることで、誤情報の拡散防止とユーザー体験向上を同時に狙っています。
AI Overviewsの仕組みと主要機能
AI Overviewsは、検索キーワードを入力した瞬間に関連ページを選別し、生成AI「Gemini」が数秒で要約を生成する二段階プロセスを採用しています。
最上部に表示される「概要スナップショット」は検索意図に紐づく情報を表示し、追加調査に役立つリンクを同時に提示するため、ユーザーは最短距離で信頼できる情報へたどり着けます。
概要スナップショット生成フロー
まず、検索アルゴリズムがクエリの主旨を推定し、リアルタイムで数十ページを抽出します。
次にGeminiが抜粋と要約を行い、重複や冗長表現を排除したうえで数行の回答を構築します。この回答が品質基準を満たした場合に限り、オーガニック検索結果の上部に挿入されます。
出典リンクと帰属カード
要約の直下には、情報源として選ばれたページがカード形式で最大数件表示されます。
クリックすると該当箇所へ直接ジャンプできるため、内容を検証しやすく、信頼性も担保されます。
カードへの採用可否は、テーマ適合度や専門性、更新頻度など複数指標の総合評価によって決まります。
追加質問チップ
AI Overviewsの下部には「もっと詳しく知りたい」「別の角度から見る」などのチップが並びます。
これを選択すると、直前の要約を踏まえた追質問が実行され、調査を段階的に深めることができます。チップの生成もGeminiが行い、ユーザーの次の疑問を予測して提示します。
プラン生成・手順提案
旅行日程やプロジェクト計画など複数ステップを要するクエリでは、Geminiがタスクを分解し、時系列に整理したプランを自動生成します。
ユーザーは提案された手順を保存・共有し、必要に応じてカスタマイズできるため、業務効率を大幅に高められます。
マルチモーダル検索との連携
画像や動画をアップロードして「この製品の概要をまとめてほしい」と指示した場合でも、Gemini Visionがビジュアル要素を解析し、同様のスナップショットを作成します。
文字・画像・音声が混在する複雑なクエリでも一貫した回答体験を提供できる点が従来検索との大きな違いです。
参考:マルチモーダルとは?最新AIの活用法や主要ツールを一挙解説!|LISKUL
品質・安全フィルター
医療や金融など高度な正確性が求められるYMYL領域では、独自の安全フィルターが二重に機能します。
リスクが高いと判定された場合、AI Overviews自体が非表示となり、従来どおりのブルーリンクのみが返されます。
この仕組みにより、誤情報の拡散を最小限に抑えながら利便性を維持しています。
AI Overviewsが表示されないこともある
AI Overviewsは常に出るわけではありません。Googleは利便性と安全性を両立させるために表示可否を細かく制御しており、条件に合わない場合は従来どおりの検索結果(いわゆるブルーリンク)のみが返されます。
ここでは表示されない主な要因を6つ紹介します。
1.YMYL領域や誤情報リスクが高いクエリ
医療・金融・法務など「Your Money or Your Life」に該当するテーマでは、誤った要約が重大な影響を及ぼす恐れがあります。
Googleの安全フィルターが「生成にはリスクが高い」と判定すると、AI Overviewsは自動的に抑制されます。
2.明確なファクトが一意に定まる質問
「日本の首都は?」のように単一の事実で答えが決まるクエリでは、要約を生成するまでもないため表示されません。
Googleは辞書カードやナレッジパネルで十分と判断し、AI Overviewsを省略します。
3.Geminiの信頼度スコアが閾値を下回った場合
候補ページが少ない、情報が断片的、相互に矛盾する――といった状況では要約品質が担保できず、モデルの信頼度スコアが基準値を下回ります。
品質確保の観点から、こうしたクエリでもAI Overviewsは非表示になります。
4.検索言語・地域がまだ対象外
現在は英語圏を中心に段階的に展開されています。未対応言語や対象外の国では、グローバルリリースまでAI Overviewsは表示されません。
試したい場合は、Search Labsで米国英語に切り替えると動作を確認できることがあります。
5.ユーザー側で実験機能をオフにしている
GoogleアカウントでSearch Labsのトグルをオフにしている場合、対象地域であってもAI Overviewsは出現しません。
ブラウザ設定や別アカウントで表示結果が異なる場合は、Labs設定を見直すと解決することがあります。
6.ページ読み込み速度やシステム負荷
検索トラフィックが集中しているタイミングやネットワーク状態が不安定なときは、生成処理がタイムアウトし、ブルーリンクだけが表示されるケースがあります。
ページを再読み込みすると表示されることもあります。
AI Overviewsのオンオフを切り替える方法
AI Overviewsは、Googleアカウントに紐づく「Search Labs」のトグルを操作するだけで、数クリックで有効・無効を切り替えられます。
ブラウザ版とモバイルアプリ版は操作手順がほぼ共通のため、利用シーンごとに気軽に切り替えて検証できる点が大きな利点です。
以下では主要な設定場所と具体的な手順を解説します。
Search Labsでの設定手順(PCブラウザ)
- Google検索ページの右上にある実験用ビーカーアイコンをクリックします。
- 「生成AIを使った検索体験(AI Overviews)」のトグルをオンにするかオフにします。
- 変更は即時反映され、次回以降の検索で設定が保持されます。ブラウザを再起動する必要はありません。
言語と地域を切り替えて利用する方法
AI Overviewsは国・言語ごとに段階的に展開されています。対象外の地域ではトグルが表示されない場合があります。
ブラウザ設定で言語を「English(United States)」に変更し、Search Labsを再度開くとトグルが表示されるケースがあります。
VPNやブラウザの言語設定を戻せば、元の検索体験にすぐ切り替えられます。
モバイルアプリ(iOS/Android)での切り替え
- Googleアプリを開き、プロフィールアイコン → 「Search Labs」を選択します。
- 「AI Overviews」のトグルをオン・オフします。モバイルデータ通信でも即座に反映されます。
- アプリのキャッシュをクリアする必要はなく、同一アカウントであればPC側も自動で設定が同期されます。
一時的に無効化したい場面で便利なコツ
QAテストや社内デモで従来検索を再現したいときは、ブックマークバーに「https://www.google.com/search?lab=0」を登録しておくと便利です。
インコグニートウィンドウを利用すると、ログイン状態を保ったまま別タブでAI Overviewsの有無を並べて比較できます。
組織管理者向けの制御(Google Workspace)
Workspace管理コンソールでは、組織単位でSearch Labsを無効化するポリシーが用意されています。
研究開発部門だけを有効化する、コンプライアンス要件が厳しい部署では無効化する、といった粒度の高い運用が可能です。
これらの設定を把握しておくと、検証フェーズやユーザビリティテストで「AI Overviewsあり/なし」の両方を瞬時に切り替えられます。ビジネスシーンでは新機能の効果測定やトラブルシューティングに役立つため、ぜひ活用してみてください。
AI Overviewsのメリット5つ
AI Overviewsを活用することで、ユーザーは短時間で信頼できる要点を把握でき、企業は自社コンテンツへの新たな露出機会を得られます。
検索体験そのものを効率化しながら、意思決定スピードとサイト流入の質を同時に高められる点が大きな魅力です。ここでは代表的なメリットを5つ紹介します。
1.意思決定スピードが向上する
従来は複数ページを行き来して情報を集める必要がありましたが、AI Overviewsでは要約スナップショットで主要ポイントを即座に確認できます。
ビジネス資料の下調べや市場動向の把握といった場面でも、判断材料が一画面で揃うため、会議準備や顧客提案のリードタイムを短縮できます。
2.調査コストと作業負担を削減できる
深掘り用リンクが最初から整理されているため、信頼性の低いページを踏むリスクが減り、情報の取捨選択にかかる手間も軽減されます。
特に長大な比較記事や専門レポートを読む前段階で要点を把握できるため、調査コスト(時間・労力)の削減が期待できます。
3.専門家ソースへ直行できる信頼性
要約の下部には引用元カードが表示され、クリックすると該当箇所へ直接アクセスできます。
ユーザーは根拠をすぐ確認できるため、データの裏付けを求めるビジネスシーンでも安心して活用できます。結果として、情報精度に対する不安を大幅に低減できます。
4.サイト運営者に新たな露出機会を提供
引用元に選定されれば、従来の検索順位に関係なく画面最上部のカードで紹介されるため、ブランド認知や指名検索の向上につながります。
高品質で専門性の高いページはAI Overviews経由の流入を獲得しやすく、ロングテールキーワード対策としても有効です。
5.検索ジャーニー短縮によるコンバージョン向上
要約によってユーザーの疑問が早期に解消されると、購入や問い合わせといった次のアクションへの移行がスムーズになります。
特にB2B領域では「調査→比較→意思決定」のステップを圧縮できるため、コンバージョン率や商談化率の向上が見込めます。
AI Overviewsのデメリット5つ
AI Overviewsは検索効率を高める一方で、誤情報のリスクや流入減少など、マーケティング施策に影響を及ぼす懸念があります。
1.誤情報・ハルシネーションが発生する可能性
生成AIは複数ソースを統合して回答を作成しますが、矛盾を含む情報を組み合わせると事実と異なる要約が表示される場合があります。
医療や金融のように正確性が求められる分野では、結果を鵜呑みにすると意思決定を誤る危険があります。
2.オーガニッククリック流入が減る恐れ
ユーザーが概要だけで満足すると、個々のページを訪問せず離脱する傾向が高まります。
特に「調べもの」中心のコンテンツはCTRが下がり、セッション数や広告収益に影響する可能性があります。
3.ブランドメッセージをコントロールしづらい
要約はAIが自動生成するため、表現や文脈を自社で調整できません。記事で強調したいポイントが圧縮され、ブランドイメージが想定と異なる形で要約されるケースも考えられます。
4.EEAT強化など運用コストが増える
引用元に選定されるには専門性・信頼性を高める追加施策が欠かせません。権威ある著者情報の整備や構造化データの充実など、コンテンツ制作とサイト保守にかかる工数が増加します。
5.表示ロジックがブラックボックス
Googleは安全フィルターや品質基準の詳細を公開していないため、どのクエリで要約が表示されるか予測しにくい状況です。
A/Bテストを行っても再現性が低く、施策効果を評価しづらい課題があります。
AI Overviews時代のSEO対策5つ
前述のとおり、AI Overviewsの普及によって検索結果は「クリックを促す場所」から「その場で疑問を解決する場所」へと変化しています。
したがって、これからのSEOは「要約に取り上げられること」「クリック後の満足度を高めること」の二軸で最適化する必要があります。
以下では、具体的な取り組みを五つの観点で整理します。
1.コンテンツ戦略の再設計 ―「答え」を冒頭で示す
ユーザーが概要だけで疑問を解決できる時代には、記事冒頭に結論と一次情報を配置し、続けて背景や事例を展開するピラミッド型の構成が有効です。
検索意図と直接結びつく見出しを増やし、AIが要約を抽出しやすい文章構造を整えましょう。
2.EEATを高める運用体制
専門家プロフィールの明示、実践データや独自調査の公開、第三者レビューの引用など、経験・権威・信頼に関わるシグナルを積極的に強化します。
執筆ガイドラインを策定し、記事ごとにソースチェックと事実確認の工程を設けると品質を安定させやすくなります。
3.構造化データとテクニカルSEOのアップデート
FAQPage、HowTo、Productなど適切なschema.orgタイプをマークアップし、検索エンジンが情報を文脈付きで理解できる状態をつくります。
あわせてモバイルページ速度とコアウェブバイタルを最適化すると、AI Overviewsの候補ページに選ばれる可能性が高まります。
4.ブランド検索とサイテーションを増やす
指名検索はAI要約の出典選定にも寄与します。ホワイトペーパー提供やウェビナー開催など、外部での言及ポイントを計画的に増やし、自然言語での引用(サイテーション)を獲得しましょう。
SNSやプレスリリースでの定期発信も効果的です。
5.CTR低下を補う新KPI設計と測定
Search Consoleでは「AI Overviews impressions」「AI Overviews clicks」が順次計測対象になっています。記事単位でのクリック率だけでなく、要約経由のブランド流入やリード獲得率まで追跡し、全体ジャーニーの最適化指標を見直しましょう。
掲載を避けたい場合の対策5つ
AI Overviewsは、基本的にオープンなウェブページを対象に要約を生成します。
従来の検索スニペットと同様、Googleにインデックスされつつ要約だけを非表示にする方法が用意されていますが、適用範囲や副作用を理解したうえで実装することが重要です。
以下では代表的なコントロール手段と注意点を解説します。
1.robotsメタタグでスニペット自体を禁止する
ページ全体の要約を避けたい場合は、<meta name=”robots”content=”nosnippet”> をhead内に追加します。
このタグはAI Overviewsを含むあらゆるスニペット生成を抑止するため、ブルーリンクの下に表示される通常のディスクリプションも生成されません。
検索結果に出しつつ要約だけを防ぎたいケースで有効ですが、クリック率低下のリスクがあります。
2.max-snippetで抜粋長をゼロに設定する
nosnippetでは露出が減りすぎると感じる場合は、<meta name=”robots”content=”max-snippet:0″> を設定し、抜粋文字数を 0に制限します。
AI Overviewsは長い要約を生成できなくなり、通常スニペットも非表示になりますが、タイトルやURLは維持されるため完全な掲載拒否にはなりません。
3.data-nosnippet属性で部分的に遮断する
記事内の特定要素をAI Overviewsから除外したいときは、<span data-nosnippet>機密情報</span> のようにマークアップします。
ページ全体をインデックスさせつつ、課金表や社外秘資料など要約に含めたくない箇所だけをブロックでき、SEO影響を最小限に抑えられます。
4.ログイン壁や動的レンダリングで保護する
会員限定記事やSaaS管理画面のヘルプなどは、そもそもクローラにフルコンテンツを返さない設計にするとAI Overviewsの対象外になります。
ただしユーザー体験やインデックス状況に直結するため、公開範囲を狭める前にビジネス影響を十分に検証してください。
5.組織ポリシーでSearch Labsを無効化させる
社内向けナレッジベースがインターネット公開されている場合、Google Workspace管理者がSearch Labsを組織単位でオフにすることで、従業員の検索画面ではAI Overviewsが表示されなくなります。
外部閲覧には影響しませんが、社内の情報流出リスクを抑制できます。
AI Overviewsに関するよくある質問7つ
最後に、AI Overviewsに関するよくある質問を紹介します。
Q. 追加料金はかかりますか?
A. 現在のところ、AI OverviewsはGoogle検索の標準機能として提供されており、ユーザーもサイト運営者も料金を支払う必要はありません。
広告掲載モデル(Google Ads)が維持されるため、企業は従来どおりリスティング広告に課金する形になります。
Q. 日本語ではいつ利用できるようになりますか?
A. 公式には「段階的に対象言語を拡大中」とアナウンスされています。2025年上期時点では英語圏が中心ですが、日本語でもSearch Labs経由の試験利用が順次解放される見込みです。
正式ロールアウトの時期は公表されていませんが、多言語展開のペースを踏まえると年内~来年にかけて順次対応する可能性が高いと予想されます。
Q. 旧SGEとの違いは何ですか?
A.SGE(Search Generative Experience)は実験名称で、機能内容はほぼ同じです。正式版では名称が「AI Overviews」に変わり、ビジネス利用を想定した追加機能(プラン生成・マルチモーダル検索など)が統合されています。
また、安全フィルターと品質基準も強化され、表示可否の精度が向上しています。
Q.AI Overviewsに自社サイトを引用してもらうにはどうすればよいですか?
A. 直接申請する方法はありませんが、以下の施策が引用選定率を高めると考えられます。
EEAT(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した一次情報の発信 -FAQPageやHowToなどの構造化データを整備 – 高速表示・モバイル最適化などテクニカルSEOの強化 – 更新頻度を保ち、新しい統計や事例を継続的に追加 検索アルゴリズムが総合評価を行うため、個別要素ではなくサイト全体の品質向上が重要です。
Q.AI Overviewsを無効にできますか?
A. 個々のユーザーはSearch Labsのトグルで簡単にオン・オフを切り替えられます。企業内ネットワークで一括無効化したい場合は、Google Workspaceの管理コンソールからLabs機能を制限するポリシーを設定できます。
Q. 要約に誤りが含まれていた場合は訂正できますか?
A. 現時点ではサイト運営者が直接内容を編集する仕組みはありません。Googleのフィードバック機能(AI Overviews右下の「フィードバック」リンク)から報告すると、モデル改善の参考にされます。
誤情報対策としては、記事に一次ソースを明示し、矛盾しない情報を提供することが最善策です。
Q. クリック率(CTR)が下がった場合の対処法は?
A. 要約閲覧だけで満足されるケースが増えるため、CTR低下は避けられません。解決策としては、 以下のようなクリック後の価値を高める取り組みが効果的です。
タイトルやメタディスクリプションに魅力的なベネフィットを明示する
ページ内に独自ダウンロード資料やチェックリストを配置し、要約後の行動を促す
Search Consoleで「AI Overviews impressions」「clicks」をトラッキングし、影響度を定量把握する
まとめ
本記事では、AI Overviewsの概要から誕生背景、仕組みと主要機能、表示されない条件、オンオフ設定手順、メリット・デメリット、AI Overviews時代のSEO最適化や掲載回避策、よくある質問について一挙に解説しました。
AI Overviewsは、Google検索結果の最上部に生成AIが要約スナップショットを提示し、深掘りリンクを併置することで「探す」作業を大幅に短縮します。
意思決定スピードの向上や調査コスト削減といったビジネスメリットが得られる一方、誤情報リスクやオーガニックCTR低下などの課題も無視できません。
そこで企業は、EEAT強化や構造化データ整備などコンテンツ品質を底上げしつつ、Search ConsoleでAI Overviews経由の表示・クリックをモニタリングし、新たなKPIで効果検証を行うことが重要です。
要約に含めたくない機密情報がある場合は、metaタグやdata-nosnippet属性を使って柔軟にコントロールしましょう。
生成AIを活用した検索体験は今後も急速に進化します。正式ロールアウト前の段階から、表示挙動をテストし、社内外のガイドラインを整備しておくことで、公開後の影響を最小限に抑えながら機会を最大化できます。
AI Overviewsの登場を、検索戦略を再設計する好機と捉え、ぜひ自社マーケティング施策に活かしてみてはいかがでしょうか。
生成AIサービス20選を一覧で比較(2025年版)
生成AIは日々のアップデートが急速で、ChatGPT、Claude、Gemini以外に業務特化の専門的な生成AIも増えてきました。
今回、今注目しておくべき生成AIツールを用途別に20個選出し、一覧表にまとめた資料をご用意しました。
サービス名・提供企業料金・AIごとの特徴・セキュリティ・利用されている分野など、一覧で比較できます。
- 導入検討の初期段階で候補を絞るとき
- 特定業務に適したツールを比較・整理するとき
- アップデートが追えていないので、一次整理を短縮したい
- 社内説明や稟議の補助資料として利用するとき
など、目的に応じてご活用ください。
特にChatGPT、Calude、Geminiについては種別(ROI改善や工数削減、リスク低減など)の導入効果事例をまとめており、利用シーンに応じた判断の補助として活用できるよう構成されています。
無料で取得できますので、ぜひお手元にダウンロードしてみてください。

