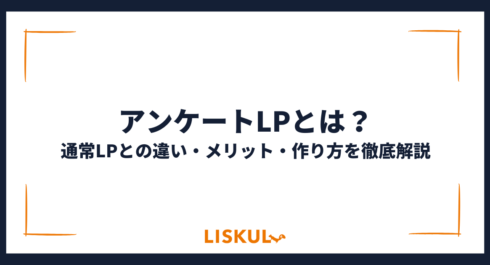
アンケートLPは、ユーザーが質問に答えることで診断結果や特典を受け取り、その引き換えに企業がリード情報を取得できる仕組みを備えたランディングページです。
従来の資料請求型LPと比べて参加のハードルが低く、リードの量と質を同時に高められる手法として注目されています。
しかし、「アンケートLP」という言葉は知っていても、自社にとって必要な手法なのか、どのように設計すれば効果が出るのかを判断できていない方も少なくありません。
この記事では、アンケートLPの概要や通常LPとの違い、導入メリット、向いている商材や業界、具体的な作り方、注意点、運用改善のポイントまでを段階的に解説します。
自社にとってアンケートLPが本当に必要かどうかを判断でき、成果につながる導入と運用のヒントを得られます。
目次
アンケートLPとは、ユーザーの回答と引き換えにリード情報を得るLPのこと
アンケートLPとは、ユーザーが質問に回答することで、その情報と引き換えに企業がリード(見込み顧客情報)を取得する形式のランディングページです。
また、いきなり商品・サービスの訴求をするのではなく、回答を通じてユーザーの関心を高めたうえで、本来のコンバージョンポイント(商品詳細ページや申込みフォームなど)へスムーズに誘導できるクッションページとしての役割も担います。
従来の資料請求型LPよりも参加のハードルが低く、かつ深い情報を得やすいため、マーケティングや営業活動の起点として活用される場面が増えています。
この形式が注目されている最大の理由は、ユーザーが「答える」という自然な行動を通じて情報提供に応じやすくなる点にあります。
一方的に「資料をダウンロードしてください」と促すのではなく、「あなたの状況に合った診断をしませんか?」というアプローチをおこなうことにより、ユーザーの参加意欲を高めることが可能です。
たとえば、以下のような形式で活用されています。
- 「3分でわかるあなたの業界別課題診断」
- 「最適なSaaSツールを選ぶための5問チェック」
- 「営業成果が伸び悩む理由を見つける自己分析アンケート」
ユーザーの入力に応じて最適なサービス提案や資料提供へつなげることができるため、単なるフォーム送信型LPよりも多くの情報を収集でき、CVR(コンバージョン率)の向上にもつながります。
アンケートLPは、情報提供と引き換えに、ユーザーにメリットを提供する仕組みをスムーズに設計できる施策であり、リードの獲得と同時にユーザーの信頼や興味を高めやすい点が最大の特徴です。
アンケートLPのメリット
アンケートLPには、通常の資料請求型LPにはない複数のメリットがあります。特に注目すべきなのは、CVRの向上・情報の質の向上・マーケティング活用のしやすさという3点です。
ここでは、それぞれのポイントについて詳しくご紹介いたします。
1.CVRが高まりやすい
アンケートLPは、ユーザーが行動しやすい設計にすることで、通常のLPよりもCVR(コンバージョン率)を高めやすくなります。
その理由は、「資料請求」や「申し込み」といった明確な意思決定を伴う行動ではなく、「質問に答える」「診断を受ける」といった軽い参加が入り口となっているためです。「まず試す」という軽い行動をきっかけにできることが、CVRを高める要因となっています。
たとえば、「あなたに合ったDXツール診断」や「たった3問で分かる課題タイプチェック」などのアンケート設計を行うことで、ユーザーは「面白そう」という感覚で自然にアクションを起こしやすくなります。
このように、ユーザーが自分の状況に合わせて回答できるため「自分ごと」として捉えやすくなり、ページの滞在時間やクリック率が向上し、結果的にCVRの改善につながるケースも多く見られます。
2.得られるリード情報の質が高い
アンケートを通じた導線設計により、ユーザーの関心や導入意欲が可視化しやすくなります。CVフォームで収集した情報も、リード理解に役立てられます。
通常のLPでは、名前・会社名・メールアドレスといった「最低限の情報」にとどまりがちですが、アンケート形式にすることで、自然な流れの中で以下のような内容を聞き出すことが可能になります。
- 業種・企業規模・担当業務などの属性情報
- 抱えている課題や不安、改善したい内容
- どのくらい導入意欲があるか(検討フェーズ)
結果として、より関心の高いユーザーからのCV獲得につながりやすく、営業やマーケ施策との連携もしやすくなります。
3.マーケティング・営業活動と連携しやすい
アンケートLPは、取得した情報をその後のマーケティングや営業活動にすぐ活用できるという点でも優れています。
アンケート導線を活用することで、流入経路や関心度に応じたマーケティング施策に発展させやすくなります。
たとえば、MA(マーケティングオートメーション)ツールと連携して「◯◯という課題を持つ人にはこのメールを送る」「温度感の高い人には営業が即フォローする」といった運用が可能になります。
CVフォームで取得した情報をもとに、ユーザーの関心度や業種に応じた対応がしやすくなります。
4.キャンペーンや初回限定オファーと相性が良い
アンケートLPは、「期間限定キャンペーン」や「初回限定特典」などのオファーと非常に相性が良い施策です。
回答完了後に特典を提示する構成にすることで、ユーザーにとっての「お得感」や「限定感」が高まり、参加率やCVRの向上が期待できます。
また、アンケートに答えることで「診断」や「提案」を受け取るという構成は、自然にプロモーション導線へ接続できるため、キャンペーンとの相乗効果が生まれやすくなります。
5.広告審査に通りやすくなる場合がある
広告出稿においては、LPの内容や表現に対して審査が厳しい媒体も存在します。
アンケートLPでは、広告クリック後にまずアンケート画面が表示され、ユーザーが回答を進めた後に詳細なオファーや資料などが提示されるため、初期表示の時点でセンシティブな表現が含まれず、審査に通過しやすくなるケースがあります。
特に、金融・美容・健康・医療系などのジャンルでは、このような構成が広告審査対策としても効果的です。
アンケートLPと通常LPとの違いは、参加ハードルと得られる情報の深さにある
アンケートLPと通常のLP(資料請求型など)では、目的・設計思想・ユーザーの心理的負担・得られる情報の質など、さまざまな点で違いがあります。
とくに、アンケートLPは「いきなり申し込みたくない」ユーザーとも接点を持てるという点で、リード獲得の可能性を広げられる施策です。
まずは、両者の主な違いを以下の表にまとめてご紹介いたします。
| 比較項目 | 通常LP(資料請求など) | アンケートLP |
|---|---|---|
| CVポイント | 資料請求、問い合わせ、トライアル申し込み | 質問への回答、診断結果の受け取り |
| 参加ハードル | 高い(比較・検討段階のユーザーが中心) | 低い(情報収集や興味段階でも参加しやすい) |
| 得られる情報 | 名前、会社名、メールアドレスなどの基本情報 | 属性、課題、検討フェーズなどのインサイト情報 |
| ユーザー体験 | 一方的に資料を受け取る形式 | 診断やチェックを通じた参加型体験 |
| CVRの傾向 | 低め(対象が検討層に限られるため) | 高め(幅広い層との接点が持ちやすく、CVに繋がりやすい) |
このように、アンケートLPは「接点をつくる」ことを重視した設計になっており、まだ比較・検討段階ではない潜在層にも訴求できるというメリットがあります。
一方、通常LPは「検討が進んでいる層」には確実に刺さりますが、それ以外のユーザーにはアクションのハードルが高く、CVに至りにくい傾向があります。
また、得られる情報の「深さ」にも明確な違いがあります。アンケートLPでは、単なる連絡先ではなく、以下のような「営業にとって価値のある情報」が得られます。
- 業種や職種などの基本属性
- 現在抱えている課題や関心テーマ
- 製品・サービスの認知度や導入検討フェーズ
このような情報は、マーケティングオートメーション(MA)や営業活動のパーソナライズ精度を大きく向上させます。
したがって、アンケートLPは、ただのCV数ではなく「接点の質」と「その後の活用」を重視する企業に向いている形式であると言えます。
アンケートLPは、リードの量と質を同時に高めたい企業に向いている
アンケートLPは、リードの「数」だけでなく「質」を同時に高めたいと考えている企業に適した手法です。
CVRが高いだけでなく、ユーザーの属性や課題感といった深い情報を取得できるため、その後の営業・マーケティング施策に活かしやすいからです。
アンケートLPが有効なケース
アンケートLPは、以下のような企業・シーンにおいて、非常に効果的です。
- LP経由の資料請求や問い合わせ数が伸び悩んでいる
- 顧客の課題やニーズが多様で、1つの訴求軸では刺さりにくい
- サービス単価が高く、比較検討期間が長い
- 営業リソースが限られており、優先順位を付けたアプローチを行いたい
- 潜在層・情報収集層とも関係を築きたい
たとえば、業界横断型のSaaSサービスやBtoBの専門サービスでは、資料請求だけでは接点を持ちづらいターゲットが多く存在します。
アンケートLPによって「あなたの業界にはこの機能が最適です」といったパーソナライズを提示することで、接点づくりと同時にニーズの把握も可能になります。
アンケートLPが適していないケース
すべての商材・企業にアンケートLPが向いているとは限りません。以下のようなケースでは、通常のLPや他の施策を優先すべき可能性があります。
- 今すぐ導入・購入を検討している「顕在層」のみに絞ってCVを獲得したい
- 商材がシンプルで、特に診断・設問を必要としない
- 一件ごとの営業単価が低く、顧客理解にコストをかけられない
- 法的・業界的に自由回答形式が難しい(例:特定の金融・医療サービス)
たとえば、無料トライアルがそのまま購入に直結するようなサービスでは、診断を挟まず最短で申し込める導線のほうが効果的です。
また、ターゲットが狭く明確な場合は、アンケート設計よりもストレートな訴求の方が成果につながることもあります。
アンケートLPが成果につながる3つの理由
アンケートLPは、単に目新しい手法ではなく、実際にCV数や営業成果といった「数値成果」につながりやすい施策です。
その背景には、構造上の3つの強みが存在します。
1.参加の心理的ハードルが低いためCVRを上げやすい
アンケートLPは、ユーザーの初回アクションが「診断に答える」「チェックを受ける」といった軽いものに設定できるため、CVRが高くなりやすい構造です。
一般的なLPでは「資料請求」や「無料相談」などの行動が求められますが、これらは「検討意欲が高い人」しか踏み込みにくく、CVRが1%未満になるケースも少なくありません。
一方、アンケートLPでは「参加のしやすさ」が強みのため、より多くのユーザーがアクションを起こしやすくなります。
- 質問に答えるだけで診断結果が見られる
- 限定レポートやチェック結果が手に入る
- 3〜5問、所要時間1分程度で完結する
その結果として、「これまでCVに至らなかった潜在層」からもリードを獲得しやすくなり、全体のCVR向上につながります。
2.得られる情報の質が高く、営業やマーケに活用しやすい
アンケートLPは、連絡先情報だけでなく、ユーザーの関心や課題、属性など、営業・マーケティングにとって有益なデータを同時に取得できます。
通常のLPフォームでは「名前・会社名・メールアドレス」程度の情報しか得られないことが多く、営業リストとしては情報が不十分になりがちです。
しかしアンケートLPでは、以下のような情報を「自然な流れで」得ることが可能です。
- 所属業種、会社規模、役職などの属性情報
- 現在抱えている業務課題や関心テーマ
- 製品・サービスに対する理解度や検討段階
CVフォームで取得した情報をもとに、MAやCRMと連携することでシナリオ設計やフォロー施策の精度を高められます。
つまり、アンケートLPは「ただのCV」ではなく、「営業とマーケに活かせる情報付きのリード」を生み出す点に強みがあります。
参考:マーケティングオートメーション(MA)とは?マーケを自動化する基礎まとめ|LISKUL
CRMとは?目的・メリット・機能から導入の流れまで一挙解説!|LISKUL
3.ユーザーの満足度が高く、ブランド体験につながる
アンケートLPは、ユーザーにとって「受けてよかった」と感じられる体験を設計できるため、ブランディングやリピート接触にも好影響を与えます。
多くのユーザーは、自社課題や最適なサービスが何かわからないまま情報収集を始めています。
その中で、アンケートLPをとおしてポジティブな体験を提供できれば、企業に対する印象や信頼感にもつながります。
- 自分の課題を整理できた
- 思っていなかった選択肢に気づけた
- 面白くて印象に残った
また、体験価値が高いほどSNSや口コミで広がる可能性もあり、「集客」と「ブランドの接点形成」を同時に実現できるのも大きな利点です。
参考:11個の要点でちゃんと理解する「ブランディングってなんなのよ?」|LISKUL
アンケートLPは、SaaS・人材・D2Cなどの商材と特に相性が良い
アンケートLPはあらゆる業界で活用可能ですが、特に成果が出やすいのは「ターゲット層が広く、比較検討の余地がある商材」です。
ここでは、相性の良い業界とそうでない業界を、それぞれ具体的にご紹介いたします。
相性がいい業界
アンケートLPと特に相性が良いのは、ユーザーごとに悩みや選ぶ基準が異なる商材です。このような業界では、属性やニーズに応じた診断や提案ができるため、アンケートという形式がユーザー体験としても自然に受け入れられやすくなります。
D2C(美容・健康系)・EC系サービス
美容や健康関連のD2C商材では、ユーザーの体質や生活習慣などの個人差に応じた提案が求められます。アンケート形式により「あなた専用」の印象を持たせることができ、CVにつながりやすくなります。
例:「肌診断」「最適なサプリメント診断」「生活習慣タイプ別商品提案」など
SaaS・IT系サービス(特に横展開型)
SaaSやIT系サービスでは、業種・職種・企業規模によってニーズが大きく異なる傾向があります。そのため、ユーザーごとに訴求軸を調整しやすいアンケートLPとの相性が高く、的確なサービス提案にもつなげやすくなります。
例:「業界別課題診断」「あなたに合った機能診断」など
人材・キャリア支援
人材関連サービスでは、ユーザーの年齢・職種・転職希望時期といった要素が、提案内容に直結します。アンケートを通じてそうした情報を引き出すことで、精度の高いキャリア支援や求人マッチングが可能になります。
例:「あなたに合った転職タイミング診断」「職種別の市場価値チェック」など
相性がそこまでよくない業界
一方、アンケートLPが必ずしもフィットしない業界もあります。以下のような商材では、アンケートを挟むことでかえってCV機会を逃す可能性があるため、導入は慎重に検討すべきです。
金融・保険など、規制や個人情報への配慮が厳しい領域
金融・保険系の領域では、取得できる情報に法的・倫理的な制約が多く存在します。
その結果、自由度の高い設問設計が難しく、アンケートLP本来の効果を出しにくくなる傾向があります。
一次接触時の導線が明確でシンプルな商材
比較・申込みが主要目的の商材では、診断や質問を挟むことが逆に障壁となり、CVRを下げる原因になります。
例:格安SIM、チケット購入、不動産査定サービスなど
検討層が極めて限定されているBtoB商材
導入を検討する企業が少数で、かつ検討期間が長いBtoB商材では、アンケートを介したリード獲得が難しくなる傾向があります。
例:大企業向けの特殊設備、産業機器、研究開発系ソリューションなど
アンケートLPの作り方8ステップ
アンケートLPは、目的やターゲット設計、質問構成から導線設計、公開後の分析まで、一連のステップを意識して構築することが成果の鍵です。
ここでは、実際にアンケートLPを設計・運用する際に押さえるべき8つのステップを、順を追ってご紹介いたします。
1.目的を明確にし、CVや収集したい情報を定義する
最初にすべきことは、「アンケートLPを通じて何を達成したいのか」を明確にすることです。
CVの目的がリード獲得なのか、商品の提案なのか、ブランディングなのかによって、設計方針は大きく変わります。
また、ユーザーからどんな情報を得たいのか(例:業種、課題、検討段階など)を明確にすることで、質問内容にも一貫性が生まれます。
2.ターゲットを絞り、課題や関心を仮説立てする
誰に対してアンケートを届けるのかを明確にすることで、質問のトーンや内容、インセンティブ設計も適切に調整できます。
ターゲットの興味・悩み・検討フェーズを仮説立てすることで、設問の精度やCVへのつなげ方も改善されます。
3.質問設計は3〜5問で完結し、選びやすさを重視する
アンケートの質問数は、少なすぎると精度が下がり、多すぎると離脱率が上がります。3〜5問を目安に、ユーザーが直感的に選べる選択肢を設けるのが理想です。
特に1問目は「はい/いいえ」や「どれに当てはまりますか?」など、スムーズに回答できる形式にすると、離脱を防ぎやすくなります。
4.インセンティブは「ユーザーにとっての価値」を具体化する
アンケートに回答してもらう代わりに、ユーザーが受け取れる価値をしっかり提示することが重要です。
例としては以下のようなものがあります。
- 診断結果(カスタマイズされた提案)
- 限定ダウンロード資料・レポート
- 無料相談・割引特典の案内
ただし、「もらって終わり」の特典ではなく、「ユーザーの次のアクションにつながる価値」であることがポイントです。
5.LPデザインは離脱を防ぐシンプルな導線設計にする
見た目や構成も、回答完了まで迷わせないシンプルな設計が重要です。質問画面はステップ数を示したり、進行バーを表示したりすることで完了イメージが持てるように工夫しましょう。
また、ファーストビューでは「どんなメリットがあるか」「何が得られるか」を明示し、ユーザーに安心感と納得感を与えることが大切です。
6.CRMやMAとの連携で即時フォロー体制を構築する
アンケートで取得した情報は、営業やメール施策にすぐ反映できる仕組みを用意しておくべきです。
MA(マーケティングオートメーション)やCRMと連携することで、属性別シナリオ配信やスコアリングも容易になります。
回答後のサンクスページや自動返信メールで次の導線(資料ダウンロードや個別相談)を案内することで、リードの温度感が高いうちにアクションを促せます。
7.広告流入元との整合性を取り、最適なターゲティングを行う
アンケートLP単体の完成度が高くても、流入経路と期待値がズレているとCVRは大きく低下します。
広告クリエイティブや導線上の文言と、アンケートの内容が一致していることが重要です。
また、ペルソナに合った媒体・ターゲティング設定ができているかも見直しましょう。
8.公開後はGAやヒートマップを使って改善を継続する
公開して終わりではなく、ユーザーの行動データを見ながら継続的に改善していくことが成果につながります。
たとえば以下のような改善ポイントがあります。
- 回答率が低い設問の順番や文言を変更する
- 離脱が多い導線にラベル追加やデザイン変更を加える
- ファーストビューの訴求をABテストで検証する
これらの改善サイクルを回すことで、初期設計では拾えなかった改善余地を見つけ、効果を伸ばしていくことが可能です。
アンケートLPを成果につなげるには、公開後の運用改善が必須
アンケートLPは、公開しただけで効果が出るものではありません。実際に成果を出している企業は、定量・定性のデータをもとに継続的な改善を行っています。
特に改善の対象となるのは、「入口(ファーストビュー)」「回答プロセス」「回答後の活用」の3つのフェーズです。
ここでは、それぞれの改善アクションについて解説します。
ファーストビューとCTAのABテストを繰り返す
最もCVRに影響を与えるのが、ユーザーが最初に目にする「ファーストビュー」とCTA(行動喚起)です。ファーストビューでは、以下のような項目が重要です。
- アンケートの目的が明確に伝わっているか
- 回答後に得られる価値(診断結果や特典など)が具体的に提示されているか
- 所要時間や質問数が明示されていて、参加しやすさが伝わるか
CTAについても、ボタン文言の工夫やボタン配置の調整により、クリック率が大きく変わることがあります。
例:「今すぐ診断を受ける」→「3問で分かる、あなたに最適な○○をチェック」
このような細かなチューニングをABテストで繰り返すことが、CVRの底上げに直結します。
設問ごとの離脱率を見て順番や文言を改善する
アンケートの中盤で離脱が多発している場合、その設問に「答えにくさ」や「疲労感」がある可能性があります。
Googleアナリティクスやヒートマップツールを活用することで、どの設問で離脱が発生しているかを可視化できます。主な改善ポイントとしては以下の通りです。
- 質問の順番を入れ替え、「答えやすい→考えさせる」順にする
- 選択肢の文言をわかりやすくする
- 必須回答を見直し、ストレスを減らす
たとえば、「あなたの部署で感じている課題は?」という設問が1問目に来ていた場合、抽象的で考える負荷が高く、離脱が増えることがあります。
そのような場合は「あなたの業種を教えてください」といった簡単な質問を先に配置することで、スムーズに進めるようになります。
取得データをメールや営業資料に即活用する
アンケートで得たリード情報は、できるだけ早く社内の営業活動やナーチャリングに活用することが重要です。回答直後の熱量が高いうちに、適切なアプローチを行うことで、商談化率やLTVの向上が期待できます。
以下は活用例です。
- MAツールと連携し、診断結果に応じたメール配信シナリオを構築する
- 営業チームへ通知を連携し、属性・課題・検討フェーズが明確なリードに優先対応する
- セミナー・個別相談の案内を、属性別にカスタマイズして送付する
これにより、「作って終わり」のLPではなく、「営業の武器になるLP」として活用することができ、事業成果にも直結します。
アンケートLPを導入する際の注意点
アンケートLPは、成果を出しやすい施策である一方で、設計や運用を誤るとCVRや情報活用の効果が大きく落ちてしまうリスクがあります。
実際に導入した企業の中でも、「成果が出なかった」「途中で運用が止まってしまった」といった声は少なくありません。
ここでは、導入前に押さえておきたい代表的な注意点を4つご紹介いたします。
質問設計の失敗はCVRの低下につながる
アンケートLPの成果を左右する最も重要な要素のひとつが「設問の設計」です。質問の内容や順番を間違えると、ユーザーが途中で離脱したり、適切な情報を得られなかったりする原因になります。
たとえば、初めの段階から抽象的で考えにくい質問を出してしまうと、回答に対する心理的負担が高まり、離脱率が急増します。
また、回答のバリエーションが少なすぎると、「自分に当てはまらない」と感じて離脱されてしまうこともあります。
そのため、設問は以下の点を意識して設計することが大切です。
- 回答しやすい順序で並べる(導入は簡単な質問から)
- 選択肢は網羅性とわかりやすさを意識する
- 質問数は3〜5問程度に抑える
特典の魅力が弱いと参加率が大きく下がる
アンケートに回答してもらうためには、「その行動に見合う価値」が必要です。提供する特典が弱い・抽象的すぎる場合、参加率(CVR)は大きく低下してしまいます。
特に、BtoB領域では「情報」に価値を感じる傾向が強いため、以下のような具体的・実用的な特典を用意することが効果的です。
- 診断結果に基づいたレポートや比較資料
- 業界別の事例集やノウハウブック
- 無料トライアルや限定キャンペーンの案内
「何がもらえるのか」「どんなメリットがあるのか」を明確に示すことで、ユーザーの期待感と行動意欲を高めることができます。
収集データを活用できないと効果は限定的になる
アンケートLPの真の価値は、「ただCVが取れた」という表面的な指標だけではありません。収集したリード情報をその後の営業・マーケ施策に活かせなければ、LPとしての価値は半減します。
実際、以下のような状態では情報の活用が進まず、CV数だけが残ってしまいます。
- 営業側が回答内容を見られない・把握していない
- MAツールやCRMと連携しておらず、ナーチャリングが行われていない
- 属性別・課題別のコンテンツや提案が用意されていない
アンケートLPを作るだけでなく、「得た情報をどう活用するか」の設計も含めて施策を構築することが成果への近道です。
プライバシー対策を怠ると法的リスクにつながる
アンケートを通じて個人情報や企業属性を取得する場合、プライバシーポリシーや利用目的の明示が不十分だと、法的リスクにつながる恐れがあります。特に、個人の行動データや自由記述などの情報を取得する場合には注意が必要です。
最低限、以下の対応は必須です。
- プライバシーポリシーへのリンクを設置する
- 利用目的を明示した上で「同意を得るチェック項目」を設ける
- 外部送信規律(Cookieやヒートマップ)の表記も忘れず対応する
安心して回答してもらうためには、「この企業はきちんとしている」と思ってもらえる設計が欠かせません。
参考:【5分で学ぶ】プライバシーポリシーとは?基礎から作り方まで一挙紹介!|LISKUL
まとめ
アンケートLPは、ユーザーの回答と引き換えにリード情報を得られる形式のランディングページであり、従来の資料請求型LPとは異なるアプローチによって、CVR向上やリード情報の質的向上が期待できる施策です。
特に、以下のような強みがあります。
- 参加ハードルが低く、CVRを高めやすい構造
- CVフォームで入力された業種やニーズなどの情報をもとに、ユーザー理解が深めやすくなる
- マーケティングオートメーションや営業資料への活用がしやすい
- 診断やチェックを通じたブランド体験を提供できる
相性が良いのは、SaaSや人材、D2Cのようにユーザーごとに課題や提案内容が異なる商材です。一方、すぐに契約につながるBtoBの高単価商材や、シンプルな導線が効果的な一部業種では、従来型LPが適している場合もあります。
導入の際は、以下の点に注意が必要です。
- 設問の設計や順番によって離脱率が大きく変わる
- 特典の価値が参加率に直結する
- データ活用設計まで含めて施策とすることが重要
- プライバシーへの配慮を十分に行う必要がある
アンケートLPは、「成果につながる仕組み」として導入すれば、リードの「量」と「質」を同時に高める有効な手段になります。
設計から運用改善まで一貫して取り組むことで、単なる接点にとどまらず、営業・マーケティング活動全体を支える強力な起点となります。
コメント